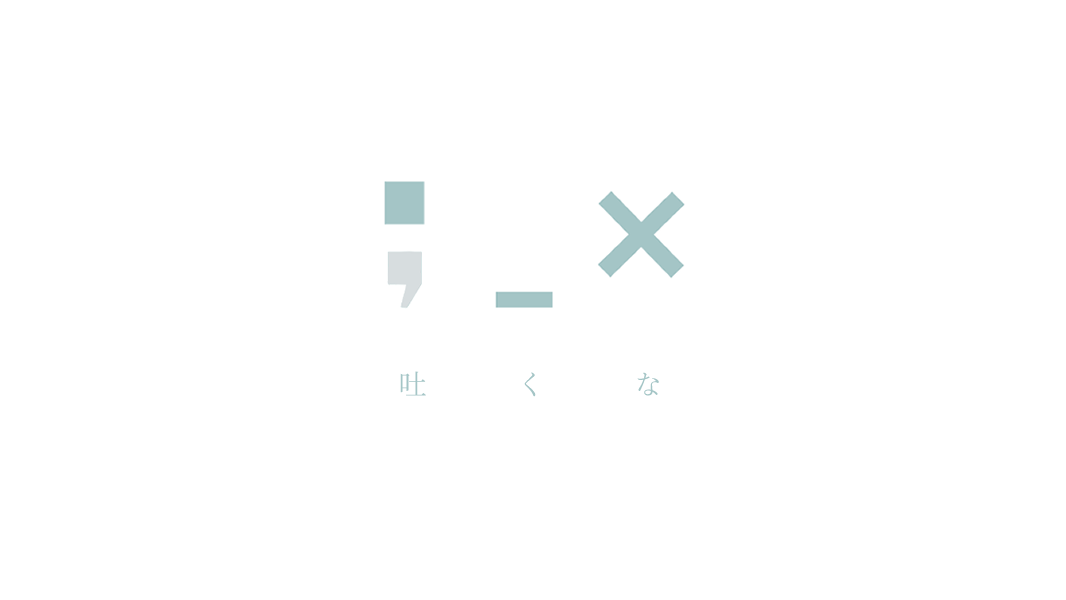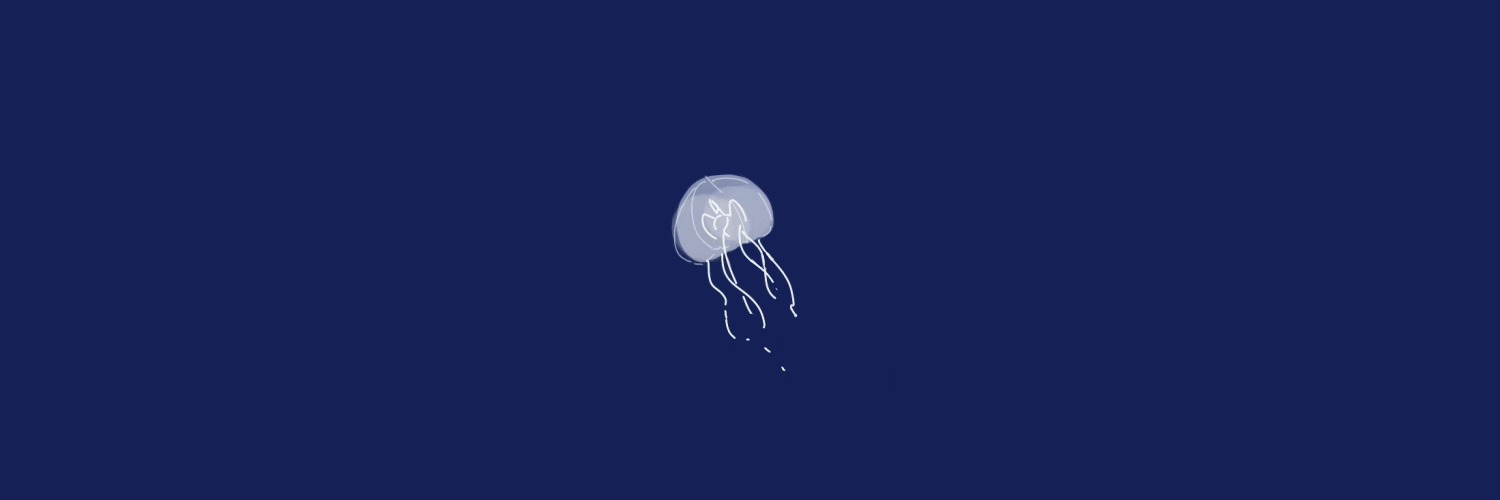うっすらと辺りが明るくなるのを感じて目を開ける。目を覚ましてまずはじめに視界に入ったのは車のドアだった。車の椅子で目覚めるのは二度目だが、そう簡単に慣れるものではない。僕は重たい身体を起き上がらせて、隣の運転席をちらりと見やる。隣人は椅子の上で、胎児のような格好でまるまって眠っている。呼吸をしているか心配になり、確認しようと覗き込むと、彼が身じろいだ。ほっとする。彼が自殺未遂をしたのは昨日の晩だ。起きてみてみたらやっぱり死んでいた、なんて冗談じゃなかった。ぼんやりと視界を白くさせる朝の空気にゆめうつつになりながら、なんとなく鞄から携帯を取り出した。両親から連絡はない。友人からも。すぐに携帯を閉じて鞄にしまう。鞄の中に入っている教科書は三日前の時間割のものだ。僕は倒してあった椅子の背もたれを元に戻して、ふと車の外に目を向けた。目の前に広がる景色に目を見開いて、慌てて隣人を揺り起こす。
「なんだよ……」
不機嫌そうに目を覚ます彼に構わず、僕は声を上げた。思っていたよりも大きな声が出て、自分でも少し驚く。そんな事はどうでもいい。
「綺麗です、海、朝日」
「はあ?」
要領を得ない僕の言葉に、彼は眉をひそめる。僕は車からおりると、運転席までまわって隣人を引っ張り出した。
「見てください、海!」
彼は僕に引っ張られて、猫背になりながらも怠そうに車を降りる。僕が海を指差すと、隣人の眠たげな目が少しだけ開いたような気がした。
朝日が海を照らしている。水色から薄ピンク色にグラデーションがかかった空の下に顔をのぞかせた太陽が、その周りの海水をキラキラと輝かせている。空の色が反射して、海まで綺麗な桃色に染まっていた。幻想的な光景だった。波が揺れるたびに輝く水面はたとえようがないほど美しく、自然に出たため息は胸に詰まっていたものを浄化させるかのようだった。半袖のシャツの隙間を涼しげな風が吹き抜ける。
「来てよかった」
僕がそう言うと彼は「そう」とだけ言って黙ってしまう。振り返ると彼はボンネットに干していたズボンを履いている所だった。どうやら雨が降る事もなく一晩で乾いたらしい。彼はベルトを着けてからポケットに手を突っ込むと、中に入っていたあのちいさな瓶を引っ張り出した。海の中でも迷う事なくポケットに留まっていたらしい。小瓶に朝日がてらりと反射する。
「なんなんですか、それ」
僕が問いかければ、彼は今度こそすんなりと答えた。
「毒」
「…………」
いくらかは予想していた答えだけれど、僕はどう返せばいいかわからずに黙ってしまう。隣人は続ける。
「違反サイトで買ったの。本当は一日目にこれ飲んで終わる予定だった」
「……そうですか」
「君のせいで狂っちゃった」
そういって、彼は不器用に笑うのだ。一日目に死ぬつもりだったのなら、どうして僕を誘ったんですか。それをもう一度問うことはしなかった。きっと気まぐれだったのだろう。
「よかったです、貴方が死ななくて」
僕がやっとの思いでそう吐き出せば、朝日を照り返していたちいさな瓶は隣人のポケットに戻された。
「どうするんですか、それ」
「ちゃんと処分するさ」
吹き抜ける風が心地いいのは彼も同じだったようで、隣人は海の方を向くと深く息を吸い込んだ。僕も真似をする。しょっぱい海の匂いが鼻をくすぐった。
「海の匂いがする」
「潮の匂いだよ」
隣人が訂正したが、何が違うのか僕にはわからない。朝日はもう高くのぼっている。
「朝ごはん、一緒に食べませんか?」
「ああ?」
車に乗り込みながら僕がそう提案すれば、隣人は怪訝そうな顔をした。朝食は食べないと、二日目の朝に話したはずだと。僕が負けじと見つめていれば、彼は目をそらしてため息をついた。
「仕方ないな」
車を少しだけ走らせて、コンビニの駐車場に止まる。昨晩、歩いて彼の着替えを買いに来たコンビニだ。今日は二人で店の中に入る。時間帯のせいなのか、相変わらず客足はなく店の中はしんとしていた。僕がおにぎりの棚を眺めている横で、彼はサンドイッチを手に取る。
「やっぱり好きなんじゃないですか、パン」
「あ?」
「仕事とか関係なくて。食べたいから食べてるんでしょう、片手で食べられるならおにぎりでもいいじゃないですか」
隣人はそれには何も返さずに、何にするの、と僕を急かした。僕はツナマヨネーズのおにぎりを棚からとって、それから炭酸を買ってもらうことにした。
「君は炭酸が好きだね」
彼はそう言って、僕の持っていたおにぎりと炭酸をカゴにいれるとレジへ向かう。そういえば、水族館でも僕は炭酸を頼んだなと思い返した。
朝食の入った袋を持って車に戻る。駐車場は空いているので迷惑にもならないだろうと車の中で食べる事にした。海が近いからか、少し開いた窓の隙間から潮のにおいが吹き抜ける。口に含んだおにぎりはすこししょっぱいような気がした。僕達は無言で、慣れない朝食を口に運ぶ。昼も夜も同じ事をしている筈なのに、朝だからというだけでこの行為が特別なように感じられた。彼はサンドイッチを食べ終わると口を拭って、僕のおにぎりのゴミもビニール袋にまとめ、コンビニのゴミ箱へと捨てに行く。
戻ってきた隣人は、運転席の外で軽く伸びをしてから車に戻った。
「帰るかあ」
「はい」
彼の呟きに、僕は答える。車はゆっくりと動き出して、コンビニの駐車場を出た。走り出すと窓の外には、空の色をした海が広がっている。太陽が高く登っても、晴れの日の海はきらびやかに輝いていた。
両親になんて言われるだろうね、と隣人が言う。僕の両親の事を言っているようだ。
「ここまで連れ回しておいて?」
「君も乗り気だったでしょ」
「まあ、そうですけど」
少し間をおいてから、もう一度口を開く。
「何も言われないかもしれないです、真面目だから、大丈夫だと思われてるかも」
「まあ心配はしてるさ」
「なんですかそれ」
隣人は答えない。さっきまですぐそばにあった潮の香りは時速五十キロのせいでいつの間にか、どこか遠くのものへと変わっていった。今鼻をかすめるのは、車に取り付けられた芳香剤のミントの香りだけだ。車はもう、僕と隣人が住むアパートのある、あの町へと向かっている。