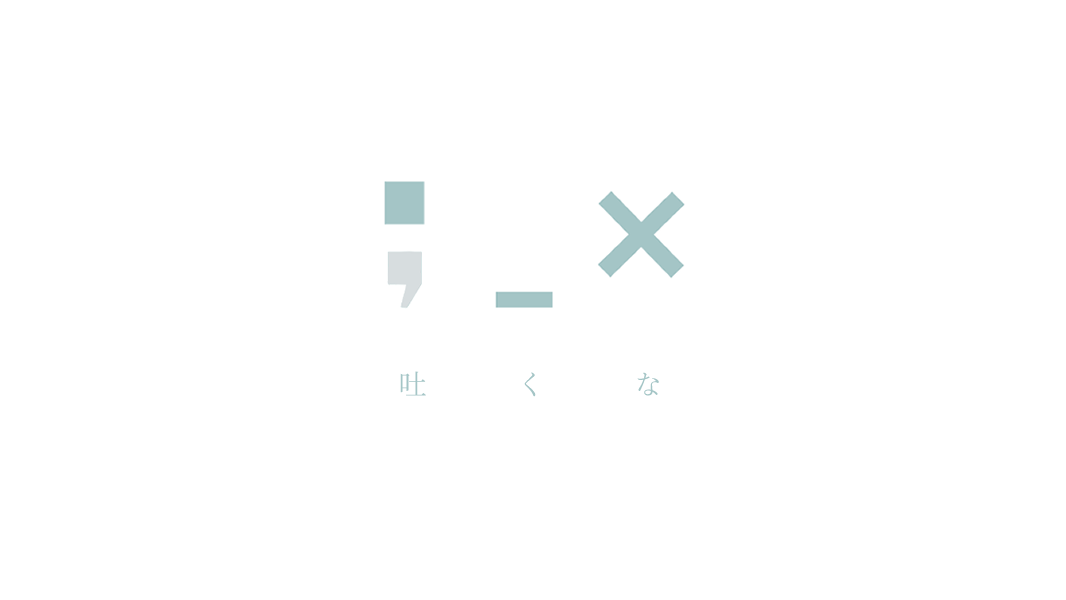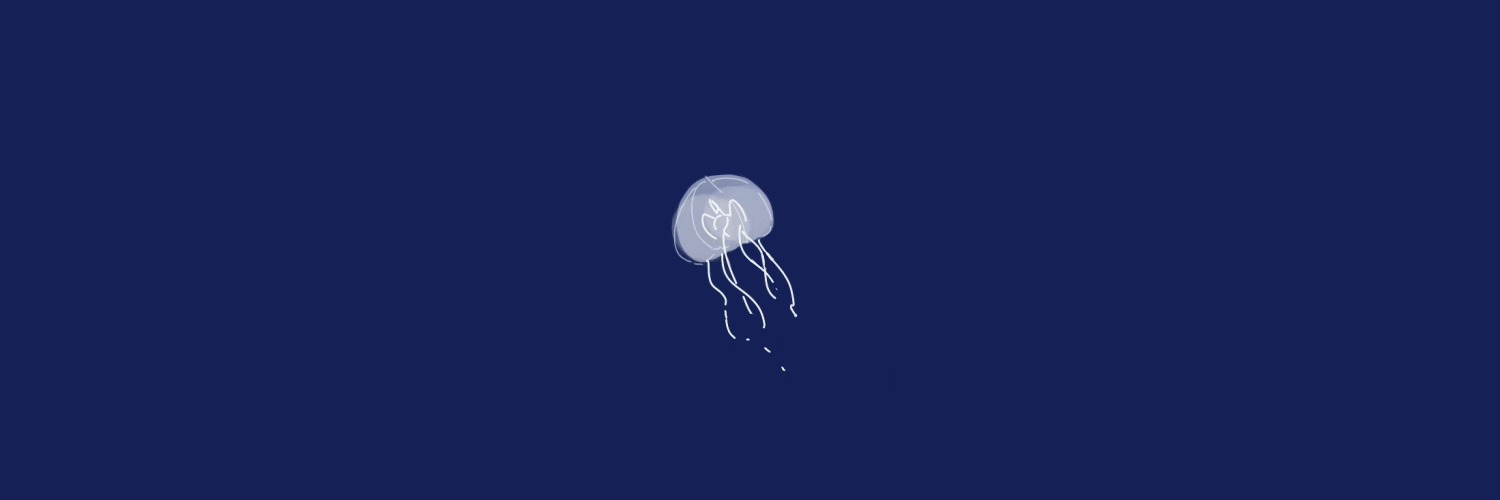空が傾いて、オレンジだった空がすっかり夜の色にすり替わったころ、やっと彼の車が泊まった。彼はポケットから財布をだして座席に置き、身軽になって運転席から降りた。彼が出ていったのにひとり残るというのもおかしいので、僕も車から降りる。月明かりだけがてらしているそこは、砂浜だった。遠くに見えるのは海だ。黒い黒い海が、月を少しだけ反射させて所々輝いている。それでも深い海は星空よりも暗かった。息を吸い込むと海の匂いがする。彼はさっさと波打ち際まで歩いていってしまうので、僕はその背中を小走りで追いかけた。
「どうして海に」
「好きなんだよ、水族館みたいだろ」
おかしなことを言う。
「水族館みたいって、水族館のほうが海を真似ているんでしょう」
「昔は水族館が本物だと思ってた。綺麗な水で綺麗に泳ぐ魚は人間が魅せるように手入れしたものだった」
海を見つめる彼の様子はなんだかおかしい。
「嫌になっちゃったんだ、電車に揺られて会社に行って仕事して、帰ってきて風呂入って適当に飯食って寝て、朝起きたらまた電車に揺られて会社に行ってさ、繰り返しじゃない」
隣人は笑いながらそう話す。僕はなんと返せばいいか考えあぐねて、それでも答えを出せないまま、先に彼が口を開いた。
「はい」
突然振り返ったかれにそれを手渡されて、つい手に取ってしまう。車の鍵だった。
「え?」
「財布に電車代くらいあるからさ、それで帰りな」
連れ回して悪かったね、と彼が言った。彼は見たことも無いようなやさしい顔をしている。僕は答えを薄々勘付いていながらも、聞かずには居られなかった。
「どうするんですか」
「試すのさ」
「なにを」
「海で死んだらクラゲになれるのか」
彼はその言葉を最後に、まず爪先を海水につけていった。迷いのない足は水の抵抗でゆっくりでありがらも深い方へ深い方へと進んでいく。どうしよう。僕は流石に追いかける事ができずに、ただ立ち止まって彼を見ていた。
彼は魚になりたかったと言っていた。それも過去形で。きっと、自由に泳ぐのを諦めている。僕みたいに。クラゲになりたいというのは、何もかも放棄してただ漂いたいということだ。そんなのは人間じゃない、クラゲでもない。せいぜい海に捨てられたビニール袋だ。放ってはおけない。このまま死なせてはいけない。自分と似ていると思ってしまった彼に、死ぬしかないと見せつけられるのは息が苦しい。僕は頭をフル回転させて、彼と過ごした数日を思い返した。どこかに、どこかに彼の歩みを止められる言葉は隠れていないか。
「僕達、あの水槽の魚みたいになれるんじゃないかって!」
彼の足は止まらない。代わりに、のんびりとした声が返ってくる。
「狭い水槽を泳ぐ魚みたいにー?」
「狭い水槽の中でも自由に泳げる魚みたいに!」
「なれないよ、魚は水槽だって気付いてないんだ」
彼は既に膝のあたりまで海水につかっている。僕は二日目のわがままを思い出した。
「あの子猫はどうするんですか!」
「ばあさんが飼うんだろ」
おばあさんは言っていた、いつでもおいで、と。それにあの人の作るご飯は美味しかった。
「見においでって言ってました!」
「…………」
彼は何も言わない。悩んでいると時間がすぎるのは早いもので、海水はもう彼の腰をこえている。
「僕と貴方は似てると思ったんです!」
「なら止めてくれるなよ」
段々彼の声が遠くなっている。このままでは……最悪の結末が頭をよぎって青ざめた。僕はどうしたらいい。海水で彼の背中の半分が見えなくなっている。ゆらゆらと月明かりを照らす暗い海に、隣人はそれがごく自然なことのように呑み込まれていく。
「ホテルから見た花火は綺麗だった!」
彼は足を止めない。それでもこちらを振り返った。
「あああああお前みたいな未来ある奴をみてるとイライラするんだよ!」
隣人がそう叫んだ。暗い海の真ん中で彼が叫んだ。その言葉が耳に入ると、考えるよりも先に言葉がぽろりとこぼれ落ちる。
「僕に未来はありますか?」
「ああ!?」
隣人はイライラした様子で聞き返した。大きくふった腕が海水を跳ねさせる。僕は彼の声に負けないよう叫んだ。
「僕に未来はありますか!」
「……あるだろ」
僕の大声に驚いたのか、彼がたじろぐ。
「本当に? 学校に行って勉強して、帰って、風呂を洗って、ご飯つくって、食べて、風呂に入って、勉強をして、寝て、また朝になって、その繰り返しが嫌になったんだ! だから貴方についてきた! 僕を見てイライラするなら、どうして誘ったんですか? どうして水族館に連れて行ってくれたんですか? 子猫を拾うのを許して、飼い主まで探してくれたんですか?」
隣人は何も言わずそっぽを向いて、また深く深くへと歩き始める。どうしたら止められる。焦ってもいい考えは出てこない。僕が隣人の立場だったら? どうしたら足を止める? ここまで戻ってくる? もっと、どうでもいい話をしよう。最後の賭けだった。
「僕、帰り道、わかりません!」
隣人がピタリと歩みを止めた、ようにみえた。実際には遠くてよくわからない。
「貴方がいないと……帰れません」
隣人は何かを考えるようにしばらく立ち止まっている。不安でどうにかなりそうな僕は、彼がこれ以上先に進まないことを只々祈るしかなかった。
暫くすると、彼は勢いよく海水を波立たせながら、怒ったような顔をしてズカズカと戻ってきた。
「嘘下手すぎだろ」
「はは……」
彼はムッと口を尖らせているけれど、死ぬ事だけは考え直してくれたようで。そのことにほっとして、力が抜ける。人生で一番頭を使った気がした。
「僕に未来があるなら、貴方にだってある筈です」
「うるせえよ」
そう返した隣人を見てある事に気が付く。彼の服はびしょ濡れだ。
「あ、あの、服、どうしましょう」
「買ってきて」
水滴がとめどなく垂れるシャツを怠そうに絞りながら、不貞腐れた様子で隣人が言った。
「ちょっと歩けばあるでしょ、コンビニでシャツと下着、ズボンは……売ってないだろうね。干しとけば乾くだろ」
「でも……」
「買いに行ってる間に死んでないか心配してる?」
図星をつかれて黙る。それもそうだろう、たった今自殺未遂をした彼がもう一度死のうとしないとは限らない。
「わかった、店の前までついてく」
僕が車の鍵をあけて座席に置かれた財布をとると、隣人は未だ不貞腐れた様子だが大人しく夜道をついてきた。コンビニまでの道のりは、歩いて十数分といったところか。チカチカと点滅を繰り返す外灯が道を薄暗く照らしている。彼が歩いたあとのコンクリートは、服に染み込んだ海水が垂れて濡れていた。彼は僕の後ろを、仕方がないといった様子でついてくる。
「仕事用の携帯壊れちゃった」
「防水じゃなかったんですか」
彼はポケットに入れっぱなしだったらしい携帯の電源ボタンを数回押して見せて、軽く頷く。
「よかったじゃないですか、辞めるんでしょう」
「……そうかもね」
コンビニの客は僕の他になく、しんと静まり返っている。店員のいらっしゃいませ、がやけに鮮明に響いた。シャツと下着とタオルだけをレジまで持っていき、隣人の財布で会計を済ます。財布の中には見た事もないほどの札束が入っていて、なんだか恐ろしくて財布を持つ手が震えてしまった。
同じ道を歩いて戻る。夜と言っても流石に外で着替えるわけにはいかないので、車までは濡れたままで戻る。
「寒くありませんか」
「寒いよ、濡れてんだぞ」
彼はそう悪態をついてから、かわいらしいくしゃみをした。
車に戻ると隣人はすぐに乗り込んでコンビニで買った下着とTシャツに着替えた。もと来ていたシャツとズボンはボンネットの上で乾かしている。雨だけは振りませんように、僕はなんとなくで信じていない神頼みをした。「着替えたよ」と声がかかったので、僕も助手席のドアから車に乗り込む。彼はTシャツにパンツという、随分おかしな格好だ。濡れているよりはマシなのだろうけれど、僕は笑ってしまった。
「お似合いですよ」
「うるせえ」
そう言って僕を睨みつける、彼の口元は笑っていた。