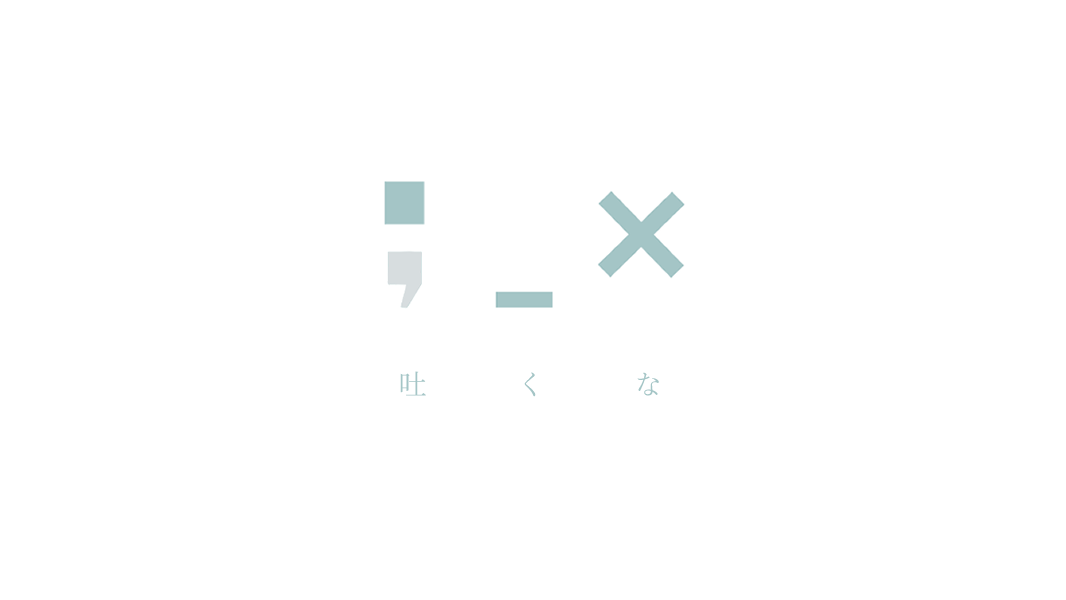喫茶店にはいると、カランとドアについたベルが鳴る。耳に心地のいい音だった。窓際の席に適当に座れば、ソファはふわりと腰を受け止めた。雰囲気のいい喫茶店である。近くの柱には禁煙の文字が貼り付けられていた。そういえば、と、今朝タバコを吸っていた隣人の姿を思い浮かべる。ぎこちなくとも、大人がタバコを吸っている姿を見るとなんだかとても歳が離れているような気になるのだ。大人と子供で、決定的に何かが違ってしまうような。年齢制限、という壁は思ったよりも深く僕に根付いている。
部屋を出る時に気がついたが、彼はホテルのゴミ箱にタバコを捨てていた。まだ何本か残っていたし安くもないだろうに――社会人の彼からすると安いのかもしれないが――とにかく彼にとってはもう必要のないものだったのだろう。
窓の外には青々とした木々が暑苦しい太陽を隠すように生えていて、その隙間からひっそりと糸のような木漏れ日が差し込んでいる。店員がメニューとお冷を運んでくると、隣人は軽く礼を言って受け取ってメニューを開いた。彼は僕にも文字が見えるよう、メニューを縦にして差し出す。気が利くな、と思った。これも大人だからなんだろうか、それとも。彼はメニューを見せながら僕に問いかける。
「どうする?」
「オムライス食べたいです」
僕はすぐさま、メニューの表紙にのっていたこの喫茶店の顔といってもいいのであろう、オムライスを指差した。隣人は「へえ」とだけ言って、ページをめくる。少し眺めて、またページをめくる。
「何頼みますか?」
「どうしよっかなあ」
彼は何度もページを行ったり来たりさせながら悩んでから、ようやく決まったらしく手を上げて店員を呼んだ。彼は店員にオムライスとチーズトースト、と注文をして、そこではじめて隣人が何を頼んだのかを知る。
「チーズトーストですか」
「悪い?」
「そういう訳では」
この人はすぐ否定的に取るな、と思う。そう思ってから、自分も人の事を言えたものじゃないと少しだけ反省をした。食べる前にうじうじ考えていても仕方がないので、本当にすこしだけ。心地よさそうな窓の外の木漏れ日を少しの間眺めていると、そこそこ早く注文した食べ物が運ばれてくる。
僕が頼んだオムライスには、可愛らしいクマのイラストがケチャップで描かれていた。
「可愛いじゃん」
彼はからかうような声をしている。
「羨ましいですか?」
「君、熟れてきたね。ムカつくなあ」
僕の返しに、彼は口を尖らせるも笑いながらチーズトーストにかぶりつく。トーストから垂れたチーズが糸を引いて、たらりと皿の上を汚した。そちらも美味しそうだったな、と思いながらオムライスを口に入れる。甘い卵と熱々のチキンライスを頬張れば、うん、やっぱりこっちでよかったと、他の食べ物などどうでもよくなった。ひとくち、ふたくちと食べすすめていきながら、ここまでの数日間の彼の行動を思い返して、こう訊ねた。
「もしかして、パンの方が好きですか」
「ん? なんの話?」
彼はチーズトーストを頬張りながら聞き返す。
「水族館でもホットドッグを頼んでたから」
「そうだっけ、なんだろ、片手で食べられるのがいいのかな。仕事しながらでも……」
そこまで声に出してから、彼は舌打ちをした。
「すみません」
僕が謝ると、彼は露骨に顔をしかめた。
「何で君が謝るの? ああ、飯が不味くなると嫌だ。面白い話してよ」
「面白い話なんてありませんよ、食べるのに集中しましょう。せっかく美味しいんだから」
僕達は無言でそれぞれのメニューを頬張る。店員からしたら仲が悪いようにみえるだろうか、なんて一瞬だけ考えて、ちょっぴり可笑しくなって僕は笑いながらスプーンを動かした。隣人がふたつめのトーストを頬張る前に口を開く。
「君、友達とかいるの」
「そこそこに」
友人関係は浅く広く、だ。そこそこに、いるともいないとも言えた。彼は「そこそこねえ」と言いながらまたトーストを口に入れる。
「いないんですか? 友達」
隣人は、学生時代はそこそこ居ると思ってたんだけどね、と呟いた。僕も将来、彼のようになるのだろうか。数日間で、そう思う事が度々あった。もしかしたら隣人は、僕のような学生時代をおくっていたのかもしれない、なんて。
「食べ終わったら行きたい所があるんだけど、ドライブに付き合ってくれるよね」
「はい」
隣人の問いに僕は快く承諾して、またオムライスを頬張った。ケチャップでかかれた可愛らしいクマの面影はもう無い。
三日目(2)
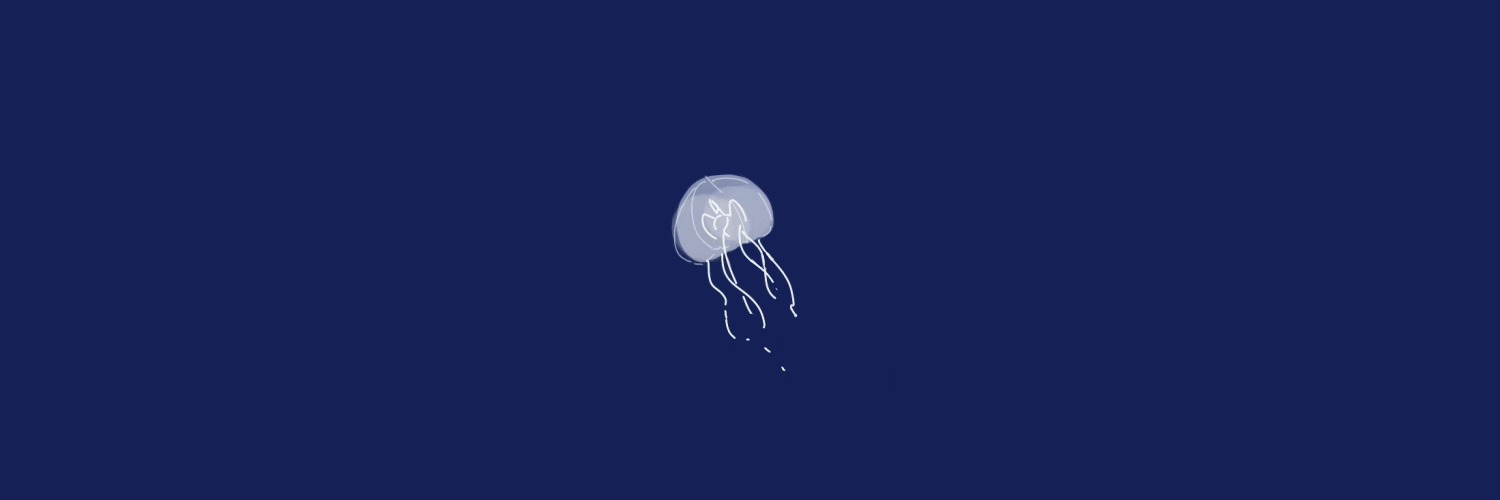 死に近かった四日間
死に近かった四日間