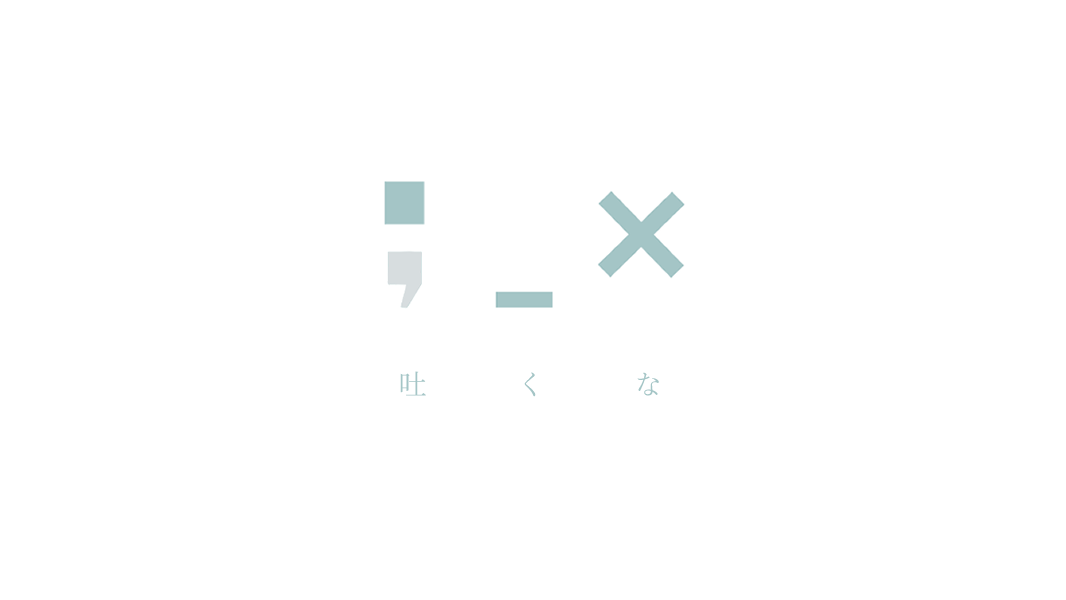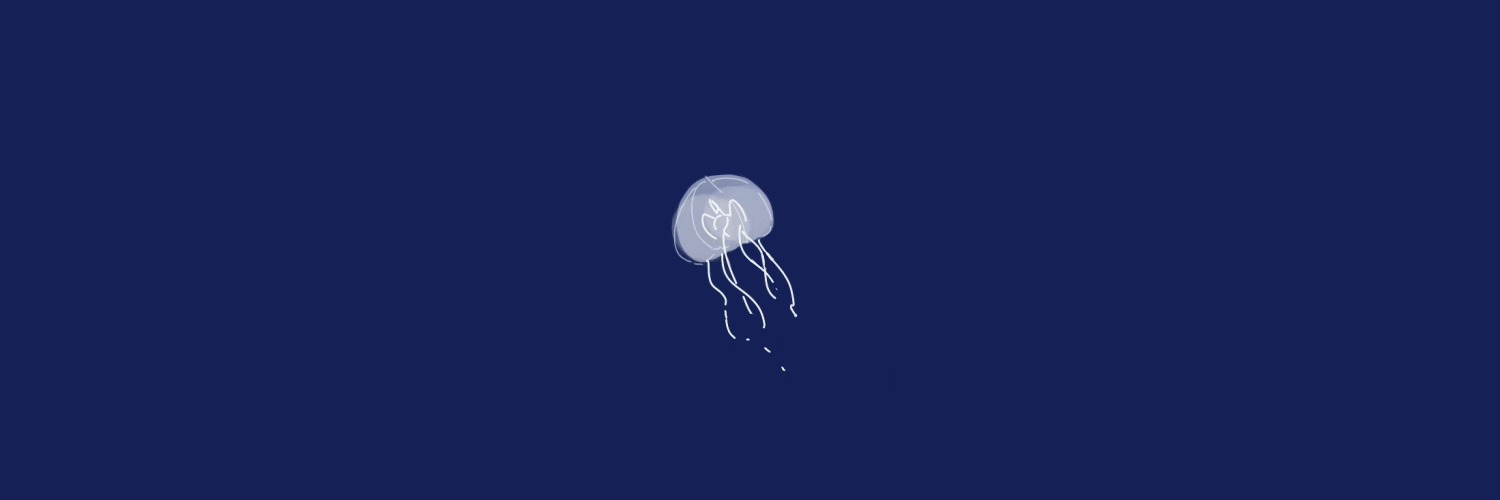「そろそろお昼だし何か食べようか」
「は、はい。フードコートがありましたよね、確か」
「じゃあそこでお昼にしよう」
イルカショーの会場からフードコートまではそれほど歩く事なく、ショーがちょうど終わった事とお昼時という時間帯のせいか、数人客が並んでいる。置かれている椅子やテーブルの数からして、休日となればものすごい混み様になるのだろう。掲げられているメニューを見上げて、隣人が指をさした。その指の先にあるのは、多分ホットドッグだ。
「美味そうだな」
「あの、いいんですか」
「何?」
「お金……」
「今更。飲み物は?」
「じゃあ、炭酸で……」
「君もホットドッグでいい?」
申し訳なくなりながらも頷く。隣人が店員にホットドックふたつと炭酸、お茶を注文する。そしてさっとお金を支払うと、僕の方を振り向いた。
「席をとっておくから。受け取ったら持ってきて」
そう言ってテラスの方へ歩いていく。その背中にわかりました、と声を掛けた。
少しの間待っていれば、ホットドッグふたつと炭酸とお茶のカップ、レシートがプレートに置かれる。そのプレートを手に持って、テラスに出た隣人を探した。彼はテラスに出てすぐ近くのテーブル席に座っていて、近付いてみると、手のひらに収まるくらいのちいさな瓶を眺めていた。白っぽい粉のようなものが入っているようだ。薬か何かだろうか、目を凝らしても僕の記憶の中に瓶の正体は存在しない。話しかける前に彼が僕に気がついて、瓶をポケットにしまい込む。その様子を見て、なんですか、とは、なんとなく聞くことができなかった。ホットドッグと飲み物の乗ったプレートをテーブルの上に置く。
「どうも」
「いえ」
彼はいただきますと小声で呟いてから、大きな口を開けてホットドッグに齧り付いた。美味いよ、と声をかけられたので、僕もひとくち口をつける。変わった特徴のないただのホットドッグだと思っていたのに、いつか食べた似たものよりほんの少し美味しいような気がした。隣人はいらずらっぽく笑っている。
「美味いだろ」
「……多分」
「ばか、こういうのは美味いって言っとくんだよ」
彼は口元にケチャップをつけたままのどかに笑む。テラスからはさっきのイルカショーの水槽が眺められて、休憩中だろうイルカたちが小さなジャンプを繰り返している。水しぶきは高く舞い上がって、それでもこちらまでは届かなかった。休憩中なのにジャンプをして、イルカは疲れないのだろうか、それとも今はショーに出る為の準備時間なのか。そうやって考えても仕方がないことを思考して、口数の少ない二人の食事時間は過ぎていく。氷の入った炭酸は当たり前に冷たく、夏の気候には美味しいけれど、ホットドッグとはあまり合わなかった。ホットドッグをお茶で流し込んでから隣人が呟く。
「この後どうする?」
「…………」
「わかりませんはナシで」
少し黙っていただけで、回答から逃げようとしていた事がバレてしまった。僕は今度こそしっかりと考えて、入場の際に渡されたパンフレットを思い返した。ポケットからパンフレットを取り出す。ポケットに入れていたせいかくしゃりと曲がっているが、その表紙にはこの水族館の顔とされているらしい大水槽が描かれている。
「……大水槽がみたいです」
「お、そんなのあるの?」
「パンフレットの表紙に乗ってました」
パンフレットをテーブル広げて見せれば、隣人は「へえ」と言って、頬についたケチャップを拭った。
「じゃあ、それを見よう」
隣人が立ち上がるので、僕もプレートをもって席から立った。プレートとゴミを片付けて、パンフレットの案内を広げる。
「ここを真っ直ぐ行ったところみたいです」
僕が指差せば、隣人がパンフレットを覗き込んで頷いた。
大水槽につくまでの道にも水槽は飾られていて、その中を同じように魚が泳いでいる。
「トンネルがあれば良かったな」
隣人が独りごちた。
「トンネルですか?」
「トンネル水槽だよ、水槽がトンネルになってる……ああもう、君水族館に疎いね」
「すみません」
うなだれる僕に、彼は指でアーチを描くようにして天井をさした。トンネルを描いているつもりなのだろう。
「魚が頭の上を通るんだ」
「それは……見てみたいですね」
「いつか行ってみたら? 探せばあるよ」
連れて行ってくれないんですか、と聞くのは図々しい気がして、僕は喋るのをやめた。足元に気を付けてくださいという看板を見かけると、床が一段降りてスロープのように下っていく。
「わお」
隣人の声に顔を上げると、パンフレットでみたままの大水槽が目に入った。隣人は水槽横のパネルに書かれた説明を読みはじめようだ。話しかけないほうがいいかと水槽の前まで移動する。
この水族館の目玉だからだろうか、入口付近やフードコートよりは人が多い。それでも平日というのは空いているものだ。客がいない場所を探して、水槽の一番手前まで近付いてみる。手のひらで水槽の表面に触れると、ひんやりと冷たい感触が手のひらから伝わった。水槽を見上げれば、遥か上まで水中が続いていて、遠くに水面がゆれている。額がつくほど顔を水槽に近付けて、その中をじっくりと、舐めるように眺めた。目の前を魚の群れが通り過ぎる。もっと近くで見たい、とずいと前のめりになれば、水槽に額が触れる。触れた額と指先の体温が奪われていく。大きさも色も違う、様々な魚たちが水槽の中を行き交っていく。ぼうっと水槽を眺めていると、不思議な感覚に陥った。まるで魚達と共に水の中にいるみたいだった。手足の力が抜けていって、さっき隣人とみたクラゲみたいに、ふわふわと身体が宙に浮いたようだ。自身が魚になったかのように、心までスッと軽くなっていった。青い水の中で自由に泳ぐ魚たちの中に混ざっていく。僕はそこではじめて、クラゲになりたい、と思った。
「こりゃあ壮大だね」
隣人の感心したような声に、現実に引き戻される。気が付くと彼は僕の後ろまで来ていて、僕の背中越しに水槽を見上げていた。
「俺もこうやって泳ぐような魚になりたかった」
「え?」
僕が聞き返すと、隣人は「なんでもないよ」と濁してしまう。この大水槽を泳ぐ魚たちに、今日見た数々の魚達、浮遊するクラゲ、華麗なジャンプを見せたショーのイルカたちもそうだ。もともと住んでいた海よりは遥かに狭いはずの水槽の中でも、魚たちは優雅に泳いでいる。そう考えると、どうしてか目の奥が熱く、呼吸が浅くなった。狭い水槽で泳ぐ魚達と、狭い世界で生活を続ける僕をどうしてか重ねてしまう。狭い水槽の中でも、魚達の泳ぎ方は自由なように、僕にはそう見えた。水槽の狭さに気が付いてしまえば、泳ぎ方を忘れてしまう。この狭い水槽の中でも上手に泳げる方法を、どうか教えてほしい。後ろ髪をひかれるような気持ちで、大水槽から手を離す。指先は水槽に体温を奪われすっかり冷たくなっている。満足したかと彼が聞いてきたので、それにはいと答えれば、すぐにその場から離れることができてしまった。