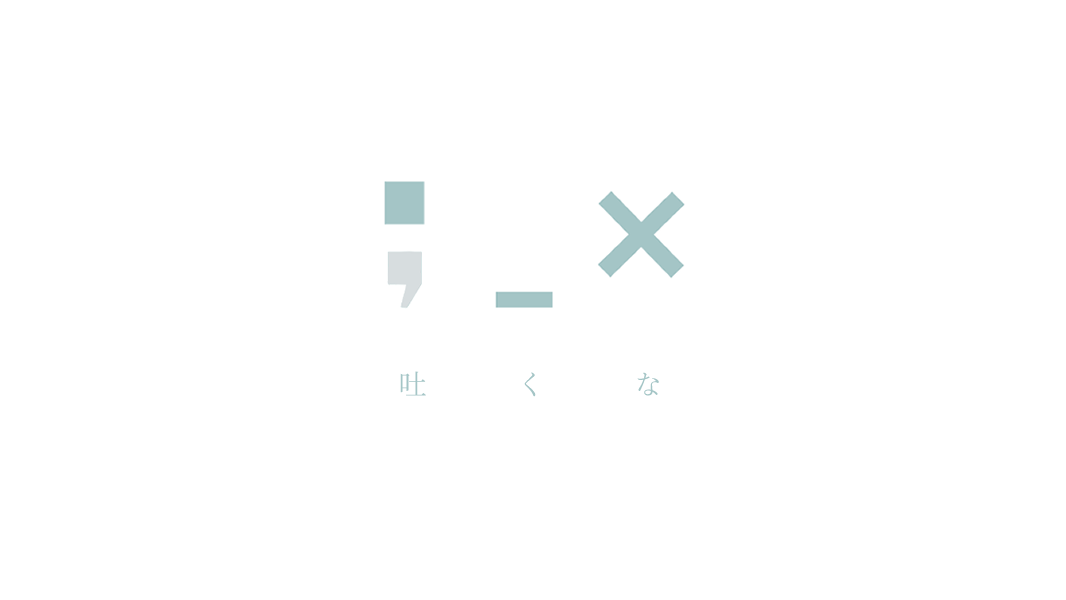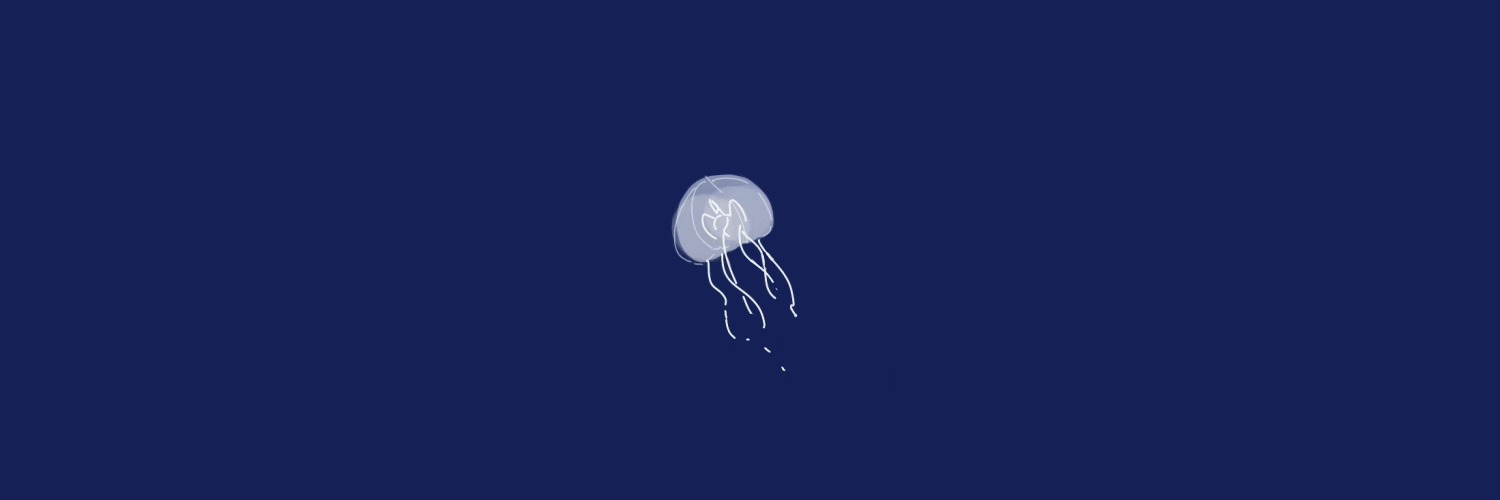車が止まったのは、だだ広い駐車場だった。彼がエンジンを切ったので、ここが目的地なのだと知る。平日だからか僕達の他に止まっている車はぽつりぽつりとまばらで、元々広い駐車場が馬鹿みたいに広く感じられる。魚や泡が至るところに描かれた建物のデザインと、駐車場に入る前の看板を見る限り、この建物は水族館だった。家族連れやカップルという言葉に納得する。周りに木が少ないからか、セミの鳴き声はあまりしなくなっていた。
「水族館ですか?」
「うん」
見ればわかるでしょといった風に、彼は早々とシートベルトを外して外へ出るので、乗り気になれない僕も慌てて助手席を降りた。クーラーの効いていた車から降りると、またじりじりと迫り来る夏の暑さが肌を焦がした。むわっとした蒸し暑さが汗を誘う。隣人は僕の事を気にかけもせずにさっさと入り口に向かってしまう。置いて行かれることはないと思いながらも、小走りで後をついていった。
「お金、持ってきてないです」
「いいよそんなの」
よくないと思ったが、それを言う前に彼はすぐにチケット売り場に向かってしまった。ガラス越しに職員に声をかけて、大人二枚のチケットと財布から出したお札を交換している。チケット売り場から戻ってきた隣人から、チケットが一枚渡された。魚のキャラクターのイラストが印刷してある。
「僕、学生ですよ」
学生料金もあるのに、とチケットを握る。
「学生証持ってないでしょ」
「持ってます」
「じゃあ失敗したな。まあいいよ、そんなに変わらない」
そう言いながらも、彼は少しだけ悔しそうにした。
入り口でパンフレットを受け取ると、水族館内に入っていく。薄暗い照明は少しだけ不安を煽って、本当にここにいていいのかという気分にさせられる。ただ隣人は車の中でも、僕は学校を、彼は仕事を休んでしまった事について一言も口にしなかった。そんな事は忘れて気兼ねなく楽しもうということなのか。それとも彼も彼で、少しの罪悪感を感じながら過ごしているのかもしれない。もしかしたら僕達は似ているのかもしれないと、なんとなくそう感じた。
狭い水槽の中を泳ぐ魚たちを、順路に従ってのんびりと眺めていく。
「水族館なんて、久しぶりですよ。よく来るんですか」
「俺も久しぶりだよ、最近はめっきり」
水槽の魚は活発に泳いでいるものもいれば、器用に水中で止まっているもの、眠っているのか沈んで動かないものもいた。水槽の隣に貼られたパネルの説明は、面倒くさくて読み飛ばす。勉強をサボって勉強をしに来たわけではない。違った日に来ていればそこも含めて楽しめたのかもしれないが、今日は活字をあまり見たくなかった。
しばし夢中になって魚を眺めていれば、隣人の姿が見当たらない事に気が付く。顔を上げてあたりを見回すと、彼はクラゲの水槽が集まったコーナーで立ち止まっていた。しばらく観察していても、動く気配もこちらに気づく気配もないので、驚かせないように声をかける。
「クラゲ、好きなんですか」
隣人は僕に気が付くと一瞬だけこちらを見やって、すぐに水槽に目を戻した。それほど好きなのかと思ったが、彼の返答は予想と違ったものだった。
「別に……でも見てると落ち着かない? ゆったりしててさ」
淡い色のクラゲが数匹、ふわふわと宙に浮くように泳いでいる。別の水槽には奇抜な模様があるものもいた。チカチカと光っているものも。そのいずれも、のんびりと、ゆったりとした動きで水中を舞っている。僕はそのクラゲの姿に、レースのカーテンを思い出した。窓を開けっ放しにした、誰もいないリビングに吹き込んだ風で膨らむレースカーテン。膨らんだカーテンは、掴もうとしても風になびいてうまく捕まらない。
「クラゲになりたいと、思ったことある?」
「は?」
隣人からの突然の問いに、僕は素っ頓狂な声を出してしまった。
「ないかな」
彼の声色は至って真面目なものだった。ならばそれに応えようと、考えてみる。クラゲになりたいと。ふわり、ゆったりと、ただ水中を漂うクラゲに。
「ないです……けど、分かるような気がします」
「そう」
水槽を覗き込む彼の黒い瞳に、真っ白なクラゲが写り込んでいた。じっとクラゲを眺めていた隣人が、僕の視線に気付いたのかこちらを向いて口を開く。
「ねえ、イルカショーみる?」
「イルカショー?」
「さっき他の客が話してた、みる?」
自分がクラゲばかり見ていたからと気を遣っているのだろうか、それとも先程の質問が気恥ずかしかったのか、隣人はぎこちない様子で誘ってきた。口元に手をあて考える。共働きの両親は忙しく、水族館に来ることなんて殆ど無かった、きっとこれからも無いだろう。せっかくここまで連れてきてもらったのだから、見てみてもいいのかもしれない。
「見てみたいです、せっかくだから」
「じゃあ、みようか」
パンフレットの案内を片手に、イルカショーのステージへと移動した。
あの広い駐車場と同じように、イルカショーの客もまばらだ。席は階段のように段々と下がっていく造りで、最前列のすぐ目の前にイルカがショーをするだろう水槽がある。空いているならと前の方の席に座ろうと通路を降りていくと、隣人に腕を捕まれ引き止められた。
「まって、濡れるって」
「濡れる?」
「イルカが跳ねるでしょ、だから濡れるって」
「そうなんですか……」
イルカショーで濡れる……記憶を引き出してみると水族館に来た記憶はぼんやりとあるが、その全てが小さい頃のもので、イルカショーを見る事自体はきっとはじめての事だった。それだからか、濡れるほどのショーというものが想像できない。いつぞやの遠足の行き先は水族館で、その予定の中にイルカショーも組み込まれていたような気がするけれど、その時は熱を出して学校を休んでいた。
どうにもこうにも、濡れたくはないので通路を戻って少し後ろの席に座る。彼が隣に座ると、まもなくイルカトレーナーが出てきて開演の挨拶がはじまった。時間ギリギリだったようだ。
トレーナーの支持に従って、イルカたちが芸を披露していく。トレーナーの持つフラフープをくぐるイルカだとか、くるくると回転するイルカだとか。
「次はあのボールにタッチしてもらいます!」
トレーナーが元気な声で上方向を示す、その手の指す方を見てみれば、かなり高い場所にボールが吊り下げられていた。
「あのボールには流石に届かないでしょう」
「みとけって」
小声で隣人に話し掛ければ、彼は自分の事のように、得意げにそう言った。合図と共に水中からイルカが高くジャンプして、口先でボールをつつく。
「すごい!」
大ジャンプの迫力をはじめて生で見た僕は、純粋に興奮して目を輝かせてしまった。高くジャンプしたイルカが水中に戻ると、大きな水しぶきが前列にかかる。確かにあれでは濡れてしまう、近くで見た方がもっと迫力があっただろうが、前列に座らないでよかったとも思った。替えの服は持ってきていないし、それまで買ってもらうわけにもいかない。
トレーナーの挨拶と、手を降るイルカを最後に可愛らしく楽しげなショーが終わる。隣人が拍手をしている事に気が付いて、僕も習って拍手をする。まばらな客たちが散り散りに水族館内に戻っていくので、僕達もそれに続いた。
「よかったね、イルカショー」
「はい、その、凄かったですね!」
隣人は微笑んている。どうしたのだろうと考えてみれば、興奮した僕を微笑ましそうに見ているんだという事に気付くと、少しだけきまりが悪くてうつむいた。