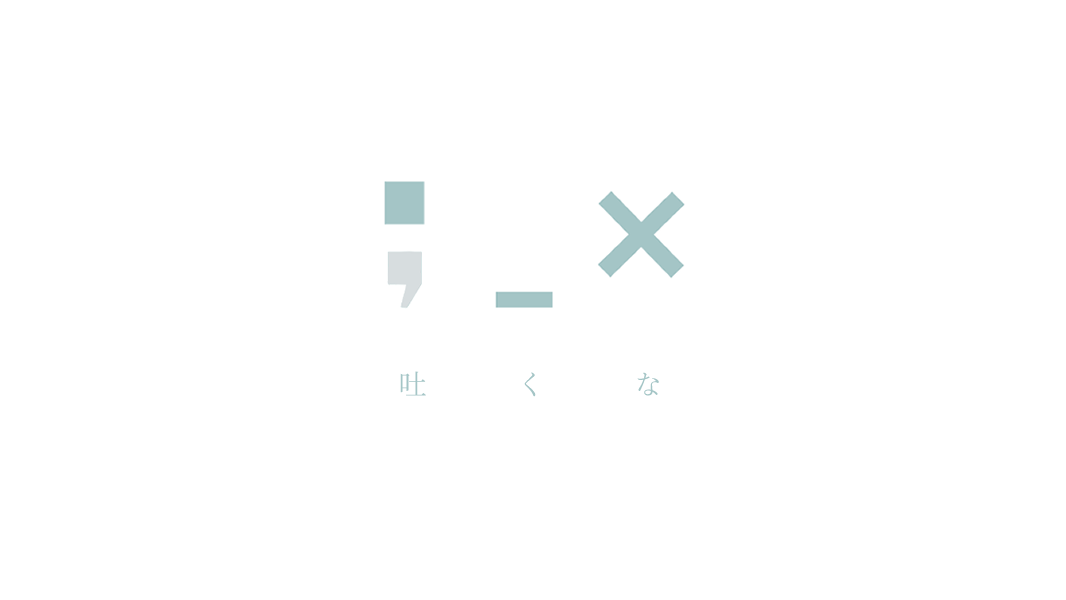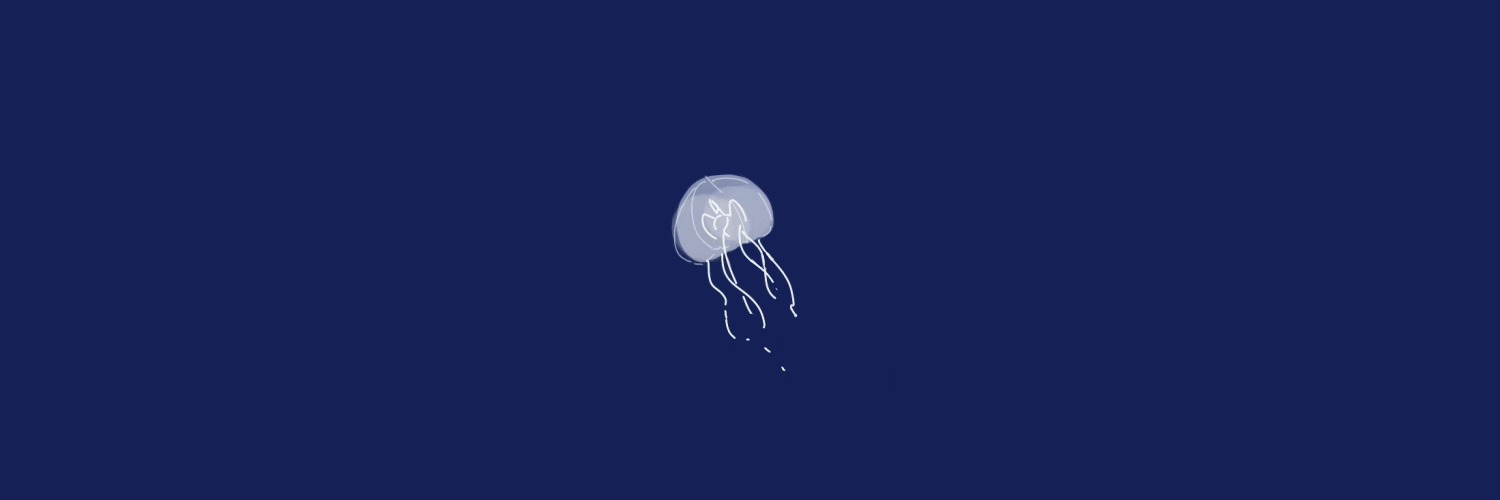少しの煙たさが鼻を掠めて薄目を開ける。ホテルの室内には、うっすらと、白い煙がただよっている。その煙を視線だけで追っていけば、その発生源は隣人が吸っているタバコからだとわかった。ベッドの隣、サイドテーブルには灰皿が置いてある。そういえば、フロントでこの部屋は喫煙可だと言っていた。それなのにあまりタバコ臭さがなかったのは、このホテルの清掃が行き届いているから、なのだろうか。隣人が灰皿に灰を落とすのを見つめていると、僕の視線に気付いた彼が口を開く。
「なに、ここ禁煙じゃないよ?」
そう言って僕を睨むような顔をして、彼はまた口元にタバコをあてがった。吸い込んでからふう、とはかれた息、また白い煙が漂う。
「いえ……父は吸わないので珍しくて」
「へえ。吸ってみる?」
「駄目ですよ」
こちらをからかうように笑う彼を、むっとして咎める。
「真面目だねえ」
そう言った彼の言葉はどこか自虐的だった。タバコを吸っている人を見慣れているわけではないが、彼の指先はどこかおぼつかない。
「あまり吸わないんでしょう、本当は」
僕がそう問い掛ければ、彼は灰皿にタバコを押し付けて火を消した。隣人はどこか諦めたように口を開く。
「仕事の付き合いで吸い始めた。残ってたし、勿体無いから吸ってみたけど、そんなにいいもんじゃあないね。煙たいし」
これは最後のタバコ、そう言って彼は灰皿にタバコを擦り付ける。何度も何度も、灰皿にタバコを擦り付けた。いままで吸っていた痕跡を消すように。そんな事をしても吸い殻が消える訳じゃないのに。
こんなふうに彼の様子を眺めながら寝ていても仕方がないので、ベッドから起き上がる。窓から差し込む日の光を見る限り、朝という時間帯は終わる頃だとわかった。サイドテーブルに備え付けられた時計を見る。時刻は十一時前、なんだかよく眠れてしまった。それもそうか、一日前は車で寝たし、その寝心地はあまりいいものではなかった……ホテルと車の寝心地を比べるのも烏滸がましいものであるが。なんとなく無言でいるのも仕方がないと思い彼に話をふる。
「昨日の花火、綺麗でしたね」
「ああ? うん、俺途中で寝ちゃったけど」
彼はやっとタバコから手を話して僕の方を向いた。どこかきょとん、としている。彼にとって花火は、それ程特別なものではなかったのだろう。その事実に少しだけがっかりする。
「うん。でも、祭りでも行かないと見れないしね。花火、よかったよ。このホテルで」
僕を気遣ってか、彼はそう付け足した。有り難いことではあるが、そんな気遣いはいらなかった。こんな気分のままではいけないと顔を洗いに行く。洗面所に置いてあった洗顔で顔を洗った。隣人にどうですか、と聞くと、彼はもうとっくに洗ったという。
それならばこれからどうするのだろうと、なんとなくホテルの部屋を眺めた。ベッドがふたつとその間においてあるサイドテーブル。あとはテーブルと、椅子が二つ。もう一度眺めてみても簡素な部屋だった。ホテルというのは何処もこうなのだろうか、あまり泊まる機会がなかったので、ここがどれ程の値段の部屋なのかはわからない。それから、チェックアウトの時間が迫っている筈なので、忘れ物がないか――といっても、それ程持ち物はないが――部屋の中を見回した。ふと隣人のベッドに目を向ければ、一日目に見たあのちいさな瓶が落ちている。きっと寝ている間にポケットから落ちてしまったのだろう。僕は側まで歩いていって、その瓶を手に取った。
「ちょっと、何? ってそれ!」
隣人は慌てた様子で僕からそれを奪い取る。パチン、と鳴った音は彼の手のひらと僕の手の甲がぶつかった際のものだ。奪い返すためとはいっても、叩かれたに等しかった。じんと痛む手をもう片方の手でさすりながら、今度は僕も、それの事を尋ねることが出来る。
「それ、何なんですか?」
「何でもいいだろ」
隣人はそっぽを向いて、瓶をポケットの奥へしまい直す。もう一度問い詰めようと口を開こうとした所、彼は焦ったように口を挟んだ。
「そろそろホテル出ないとな時間だろ、忘れ物ないか?」
あきらかに話を逸らそうとしている。
「忘れ物もなにも、ほとんど車に置いてきましたから」
「そうか」
「あの」
僕が声をかけるも、隣人は財布と携帯さっさとポケットにいれて、部屋を出ていこうとしてしまう。
「喫茶店でも行ってさ、早いけど昼飯にしよう」
「……はい」
そうまくし立てて部屋を出る隣人に、僕はついていくしかなかった。彼の勢いに押されたこともあるけれど、実を言えば、食欲にも負けた。昨日おばあさんの家で温かいご飯を食べてから、どうしてかいつもより腹が空きやすくなっている気がするのだ。これ以上口を挟むなら昼食は奢らないと言われてしまっても困るし、ここで置いて行かれては帰り方もわからない。大人しく彼についていくことにした。ここまでの水族館に猫の餌代、ご飯代、それにホテル代まで払ってもらっているのだから、彼の気に触るような事はあまりしないほうがいい。僕はただ、ついてくることを許されているだけだ。本当ならお荷物のはずだった。
フロントでチェックアウトを済ませて、ここ数日で見慣れてしまったシルバーのセダンの元へ帰ってくる。ホテルの駐車場の、コンクリートから照り返す熱で、そういえば外は夏だったんだと思い出す。室内はどこもクーラーが効いていて、快適すぎるくらいだった。彼は手慣れた様子で運転的に乗り込んで、僕も当たり前のように助手席に乗り込む。
「この辺りに喫茶店があるんですか?」
「ホテルの人が言ってた。穴場なんだってさ」
「へえ」
少しの空白のあと、隣人が、あーと喉をならして、つたない様子で口を開いた。
「あの瓶さ、ラムネだよ。紛らわしいことしてごめんね」
彼はそう言って頭を掻く。絶対に嘘だと思った。それでも僕は、不器用に笑う彼に、嘘にしか聞こえないとは伝えられなかった。車のエンジンがかかると共にクーラーが作動して、あのミント系の芳香剤が香ってくる。
「ミント、好きですか」
「ん?」
「車の芳香剤」
空調に取り付けられたそれを指差して僕が尋ねると、隣人は首を傾ける。
「変なとこ気が付くね。適当に買っただけ。柑橘系のが好きかも」
「そうなんですか」
ゆっくりと車が動き出して、駐車場から出て行く。
「僕はミント好きですけど」
彼は行き交う車を見つめながら、そうかよ、と言った。