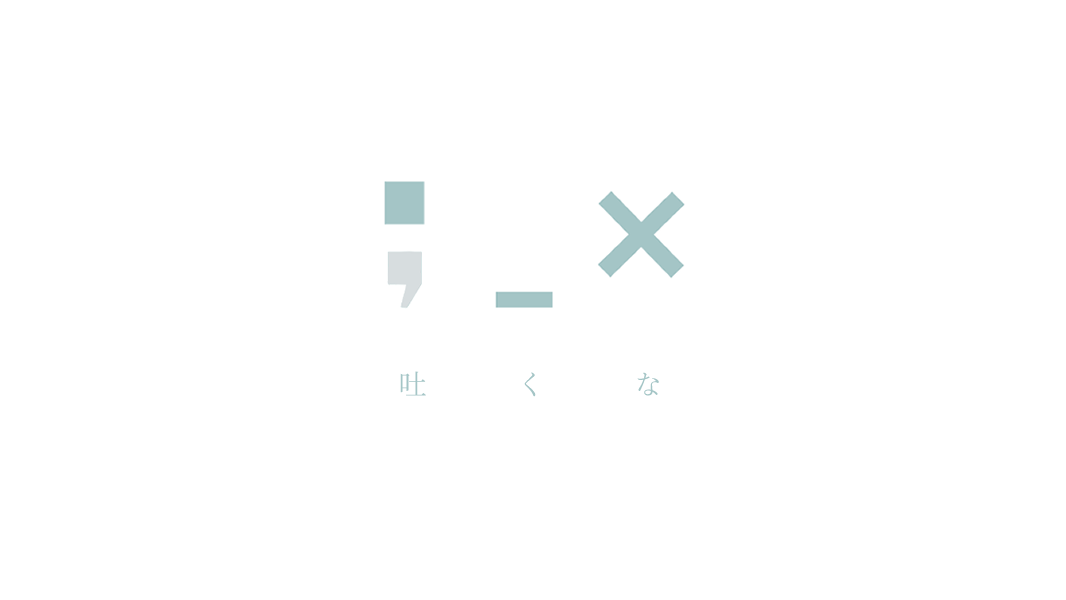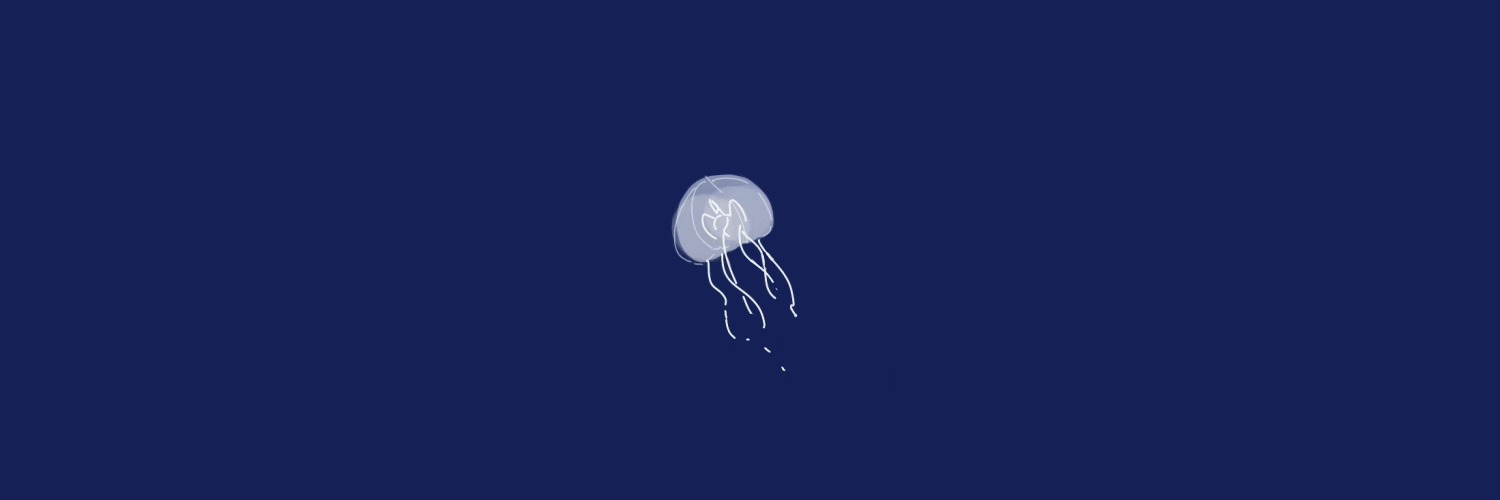ご飯を食べ終わったあと、僕は隣人とおばあさんが世間話をするのをなんとなく聞いていた。うまく相槌でもうてればいいのだけれど、それは知らないニュースの話だったり、隣人が前に住んでいたというアパートの人の話だったりしたので、ただ、聞いていた。しばらくそんな時間が続いて、日が落ちてきた頃、居間の高い所に飾ってあった振り子時計が丁度三回鳴ったのにおばあさんが気が付くと、ついにこの家からお暇する事になった。おばあさんが玄関まで見送りに来てくれると、その後ろを子猫も着いてきた。すっかりなついていて、猫はもうこの家の子になったんだなあ、と僕は思う。曖昧な嫉妬は消えていた。
「いつでも来てね、猫ちゃんの成長でも見においで」
「はい、ありがとうございます」
隣人に続いて僕も礼を言う。
「いいの、こちらこそありがとう。家族が増えて嬉しいわ」
無言で車に乗り込む。車が走り出してからも、彼も僕もひとことも声を発さずに終始無言だった。何か声を出さねばと思い必死に考える。子猫の騒動に巻き込んでしまったのは僕であるし、お礼をしなければと口を開いた。
「あの、ありがとうございました」
「いーえ」
隣人はそれだけ言うとまた無言になった。信号が赤になり車が停止する。車内がしんと静まり返る。そういえば、いつの間にか雨がやんでいる。僕は車の中の静かで重たい空気が嫌になって、隣人にこう訊ねた。
「……怒ってますか」
「別に……」
「ごめんなさい」
その声から怒っているのだと推測して、僕がしょげこむと、それを見た隣人はああ、と首を降った。
「違う違う」
君のせいじゃないよ、と彼がどこかぎこちない様子で僕の肩を叩く。
「ひさしぶりに暖かいご飯なんて食べたよなって思ってさ、慣れてないから、どうすればいいかわかんないだけ」
彼はそう言ってこちらを見やり、照れたように笑っていた。また、似ていると思う。ひさしぶりにあたたかいご飯を食べたのは僕も同じだ、と思った。
「僕もです」
「ん?」
「僕もです、ご飯。いや、いつも自分で作ってるので、冷めないうちに食べるんですけど、そうじゃなくて、ひとがつくった暖かいご飯ってひさしぶりで」
信号が青に変わる。隣人は不格好にアクセルを踏みながら、僕の言葉に小さく「そう」とだけ返した。
「今日はホテルにでも泊まるかあ」
彼が突然、明るい声を出す。驚いて目を向けたけれど彼は遠く前を向いていた。
「お金ならあるんだ、出掛ける前に下ろしてきたから。いい部屋取ってあげる」
「そんな、いいです、やめてください」
これ以上彼にお金を使ってもらうのは気が引けて、断る。彼は譲らなかった。運転しながらも僕に詰め寄る。
「そう? また車で寝たい? 風呂も入らないで?」
「……普通の部屋でいいです」
「なら、普通の部屋で」
彼はにっこりと悪そうな笑みを浮かべた。その笑みは、彼が最初に僕を誘った時と同じように見えた。車はホテルへ向かっている。
三件ほどホテルをまわって、やっとキャンセルが出たという部屋まで辿り着いた。シングルベッドが二つ並んでいる簡素な部屋だ。部屋の大きな窓から望める夜景はそこそこ綺麗で、僕は風呂上がりの湿った髪をタオルで撫でつけながら窓の外を眺めていた。コンビニの夕ごはんはもう飲み込んでしまったので、そのくらいしかやることも無い。
「楽しいか? 外ばっか見てて」
ベッドに寝転んで夕飯のパンを貪る隣人に、他にやる事も無いでしょう、と返す。彼はそれもそうだなと呟いて、ポケットから古びた携帯を取り出した。
「誰かから連絡が来てるんですか」
「どうせ会社だけ。電源切ってるんだけど癖でさ」
どうやら彼の仕事は、かなりの激務だったらしい。会社の事を語る彼の暗い表情を見ればいやでもそれがわかった。学生の僕はそれについて何も言えなく、ただ外を眺める。ぽつり、ぽつりと不規則に着いたビルの明かりはこちらから見れば綺麗だけれど、知らぬ人々が残業をしている証なのだろう。夜景を作り上げている人間の憔悴を、この夜景を望むどれほどの人間が感じ取っているのだろうか。そう考えれば先程まで綺麗だと感じていた夜景がなんだか虚しいものにみえて、窓から目をそらした。
「あ」
隣人の声に、思考が現実に引き戻される。振向けば彼はベッドの上にあぐらをかいて、僕が先程まで眺めていた窓の外に目を向けていた。
「どうかしましたか」
「花火」
「はい?」
彼が指差す僕の後ろで、ドン、と聞き覚えのある音が鳴る。夏祭りの時期に、よく耳にする音だった。振り返って遠くの夜空を望む。夜景の上の澄み切った空に向かって、一筋の閃光が上っていく。光は空の上で花開いて、それは大きな花火となった。光がキラキラと散っていった後に、ドン、とまた大きな音が鳴る。夜空に輝く光の花は次々に打ち上げられて、夜景の上を彩っていく。無数に光るビルの光の上で、それは霞むことなく咲き誇った。
「何処かで祭りでもやってるのかねえ」
隣人はのんきにそう呟いた。
「……綺麗ですね」
「まあね」
彼がどんな顔をして花火を見ているのだろうかと不思議に思って顔をむければ、彼も僕の方に目を向けて無器用に笑った。僕もそれに口角をあげて返す。彼もこの花火をみて、綺麗だと感じていればいいと考えた。隣人と僕はどこか似ているから、この感じ方も同じならいいと。彼が手元のスイッチで部屋の電気を消した。暗い部屋からみえる花火はより一層鮮やかで、ヒュウという音と共に打ち上げられて、花開いたのち散っていく姿まで美しい。僕はその光景に釘付けになった。その時間はもしかすると短かったのかもしれないけれど、僕にはとても長い時間のように感じられた。
夜空がしんと静かになるまで、必死に窓の外の花火を目で追っていた。