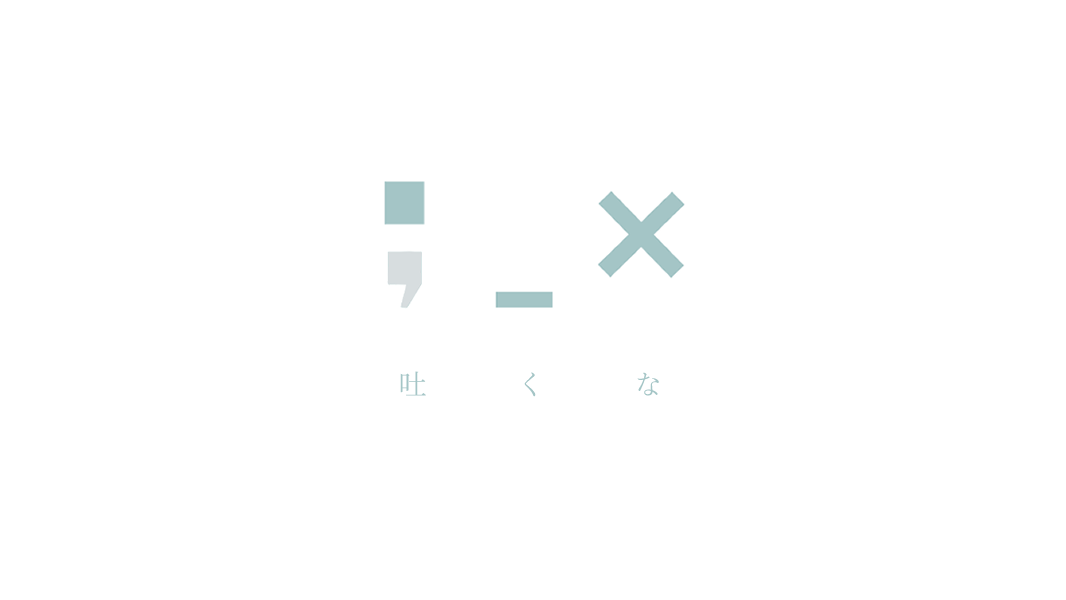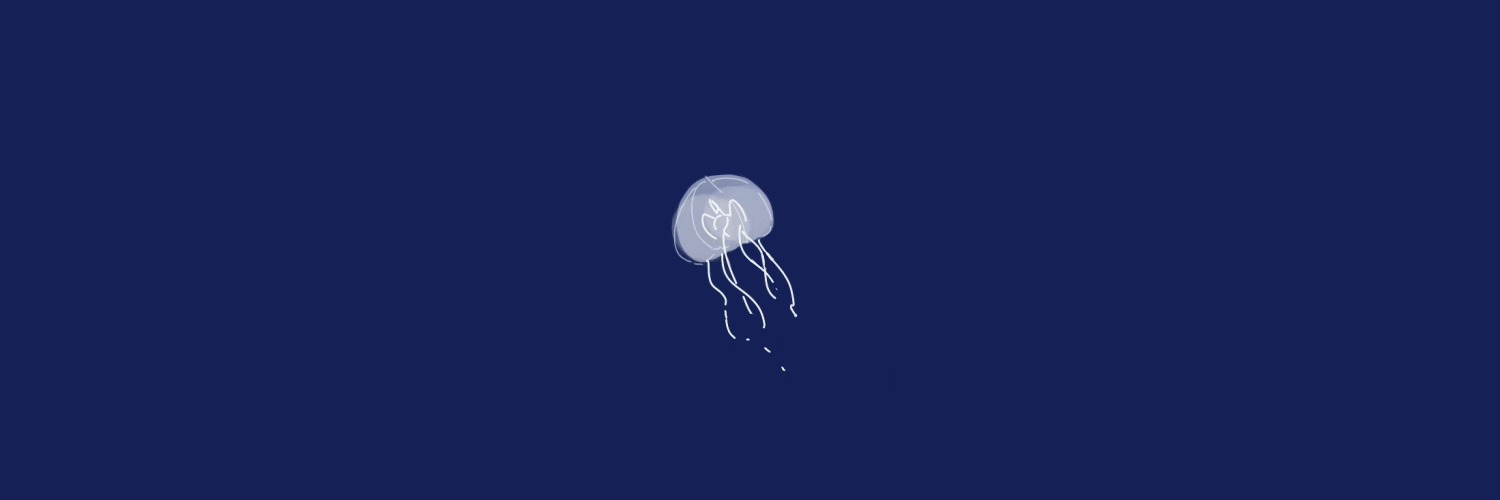いつまでたっても雨が降り止む様子はない。それどころか、子猫を拾ったその時より雨の降りが強くなってさえいるような気がする。隣人は首を傾けながら僕に問い掛けた。
「こいつ、どうするつもり?」
「……どうしましょう」
まず雨が降りやまないことが問題だ。そして、もし雨が止んだとしても、このままここに放して、この子猫は生きていけるのだろうか。この子を拾って中途半端に助けたことはエゴだったのだろうか。
「あー……知り合いに飼えないか聞いてみるよ」
悩んでいる僕を見るに見かねてか、彼はそう言うとポケットからスマートフォンを取り出して、いくつか操作をすると通話ボタンを押す。相手は数コールで出たようで、彼が電話に向かって話しだした。
「どうも、ええ俺です。前に猫を飼いたいって……」
隣で漏れ聞こえる会話の内容を必死に追っていく。電話越しの声は上手く聞き取れない。断られたら今度こそ、猫をどうするのか考えなければならない。こういう場合って、どうするのが正解なんだっけ、考えるも、今まで猫を飼ったことなどない上それほど興味もなかった僕に答えが出せるはずもなかった。隣人は電話に向かって相槌をうっていて、しばらくするとスマートフォンを耳から放した。電話を切った隣人がこちらを向く。
「飼えるって、今すぐ来いとさ。いいよな」
その答えに、心底ほっとする。
「いいんですか」
「うん、すぐ近くだよ」
僕がシートベルトをすると、車は迷いなく動き出した。
車で走ること数十分、といった所だろうか。見上げた先に見えたのは小綺麗な和風の一軒家だった。車は路肩にとまって、僕は彼の後に続いて車から降りる。段ボールは子猫がはいっているというのに想像したより遥かに軽く、驚きながらも両手でそれをかかえた。空から落ちてくる雨粒を遮るように隣人が僕と子猫の上に傘をあてがう。彼は猫の餌が入っているコンビニの袋を持っていた。
「すみません」
「こっち」
僕の謝罪を知らぬふりした隣人に誘導されて、その家の玄関まで歩いた。彼がインターホンを押す。雨音にまぎれて、家の中を人が歩いている音が耳に入った。そこで待っていれば引き戸が開けられて、おばあさんが顔を出す。おばあさんは隣人の顔を見るとすぐに笑顔になって、濡れるでしょう、と僕達を玄関の中へと招いた。
「いらっしゃい。久しぶりね」
ほがらかに笑むおばあさんに、隣人が応対する。
「お久しぶりです。すみません、突然」
「いいの、いいの。そちらの子は?」
おばあさんが僕を見やった。その真っ直ぐな微笑みにうろたえながら、なんとか挨拶をする。
「は、はじめまして……」
「今のアパートの隣に住んでる高校生です。子猫を拾ったのもこの子で」
「そうなのね。どうぞあがって。はやく子猫が見たいの」
おばあさんに勧められて、僕達は靴をぬいで家にあがらせてもらうことになった。廊下を少し進んで、居間に案内される。そこには大きなテーブルと、座布団が二枚敷いてあり、家はあたらしいのか畳のにおいがした。おばあさんは待っててね、と隣の部屋へ消えていく。
「前住んでたアパートの大家さん」
「……そうなんですか」
「気になるって顔してたでしょ」
それはそうですけど、と声を出そうとした所に、おばあさんが戻ってくる。
「雨の中大変だったでしょう」
彼女はお盆の上に湯呑みを三つと、お煎餅ののせられたカゴを運んできた。それを見た隣人が口を開く。
「すみません、お構いなく」
彼がおばあさんに頭を下げるのをみて、慌てて僕も同じようにした。大人の会話を見せつけられているようでなんだか居心地が悪い。
「その段ボールの中が猫ちゃん?」
おばあさんが目を輝かせながら僕の膝の上にのった段ボールを見やった。突然目を向けられて、あたふたしながら段ボールをさしだす。
「っはい、見ますか……」
「ええ」
彼女はにっこりと、やさしく微笑んだ。段ボールの蓋を開ければ、子猫はにゃあ、と甘えたように鳴く。おばあさんは微笑みをより一層強くして子猫を眺めている。
「まあ可愛い。まだ小さいねえ」
「人懐こい子ですよ、撫でてみます?」
隣人の言葉でおばあさんが子猫の前に手を差し出せば、子猫はその指に擦り寄った。
「うちのこになるかい?」
おばあさんがそう言うと、子猫はまたにゃあと鳴いた。
「よく鳴く子だこと、かわいいねえ」
「よかったな」
隣人が子猫に笑顔を向ける。僕はどうしてか、曖昧な気持ちを精算できずに愛想笑いをした。雨にずぶ濡れだったのを拾いあげたときと何ら変わらず、子猫は可愛らしく鳴いている。
「そろそろ失礼します」
隣人がそう言って立ち上がるので、僕も席をたとうとした。そこにおばあさんが口を挟む。
「あら待って、時間はある? せっかく来たんだからご飯食べていきなさい。どうせ朝たべてないんでしょ」
「えっと……」
隣人は困った顔をする。彼がたじろいでいるのはなんだか珍しいと、僕は他人事のように目の前で行われているやり取りを眺めていた。
「お昼っていう時間でもないけど……今持ってくるからね」
おばあさんがさっさと部屋を出ていってしまうと、隣人がため息をついた。
「こういう人なんだ」
そう言って眉を下げた隣人の表情はたしかに困っていたけれど、それよりもほんの少しだけ嬉しそうに見えた。
おばあさんが運んできてくれたのは、具だくさんの肉じゃがに、醤油のきいた卵焼き。豆腐とわかめの味噌汁と、おそらく炊きたてであろうごはん。が三人分。そのすべてに湯気が立っている。その見た目と匂いにつられて、空腹感が顔を覗かせた。そういえば昨日の夜は隣人が持っていたお菓子ですませたし、朝は食べていないのだからあたりまえだ。
「簡単なものでごめんなさいね」
「いえ……」
「いただきます」
「……いただきます」
隣人がそれを口に運ぶのを見届けてから、僕もごはんを口に入れる。舌がやけどしそうなほどあたたかいごはんをゆっくり咀嚼する。ひとがつくるご飯は久しぶりに食べたし、こうやって誰かとご飯を食べる事自体久しぶりだった。こういう時はどうしたらいいんだっけ、と考えて、思い付かないのでとりあえず、思った事を口にする。
「美味しいです……」
「まあ、よかった」
おばあさんはやっぱり、嬉しそうに微笑んだ。