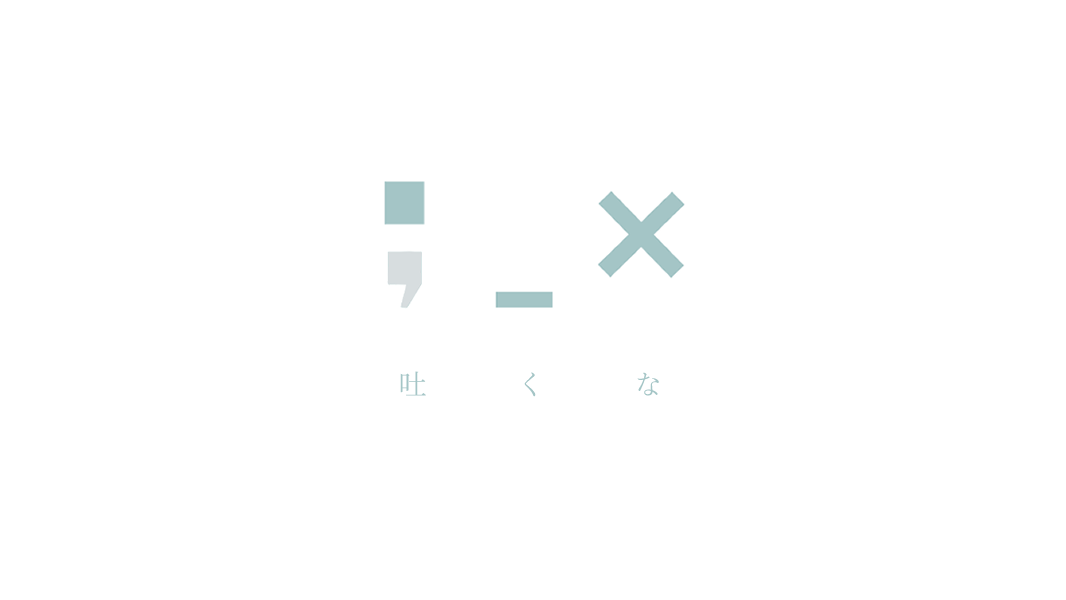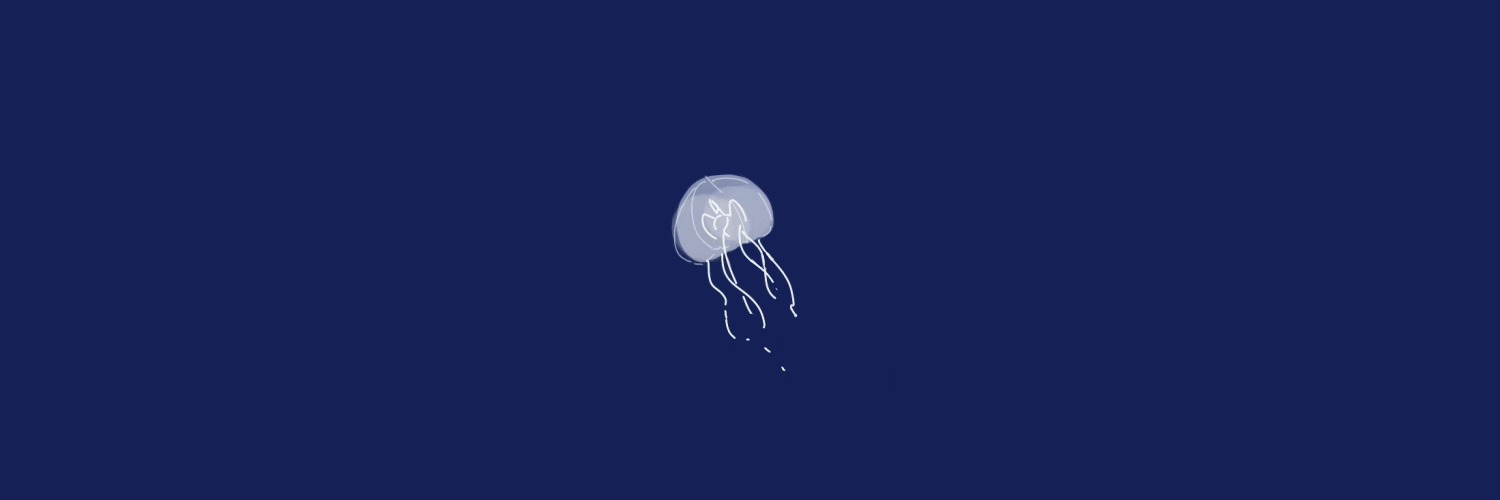目を覚ましてまず耳に入ってきたのは静かな雨音だった。無理な体制で寝たせいか体の節々に妙なだるさがある。雨が車の屋根を叩く音が強くなるのを感じると、僕はやっと重たい瞼をもちあげて窓の外を眺めた。窓を伝う雨は絶え間なく、じっと眺めていればそのうちぼんやりとした頭が覚醒していく。僕はだるさの消えない身体を起こすと、足元に置いておいた鞄からスマートフォンを取り出して電源を入れた。二件、メールが届いている。父と母からだった。本文は心配するような内容と、どこにいるのかという質問。さてどうしようかと悩んでいれば、隣から声が掛かる。
「どうした?」
隣人だ。彼は眠たげな眼をこすりながら僕の手元のスマートフォンに目をやった。
「親からです、昨日はどうしたのって」
正直にそう告げると、彼は「返しておけば」とあくびをする。
「なんて返すんですか?」
「家出してますって」
「…………」
僕は返信の内容をひとしきり考え悩んでから、両親に一斉メールで無事であることだけ送信した。心配しないで、と。隣人は気怠げに寝返りをうつ。
「なんだって?」
「とりあえず、無事だって返事しました」
「ふうん」
彼は自分から聞いておいて、興味がなさそうに起き上がった。椅子の背をもとの高さまで戻して調節している。僕もスマートフォンを放るように鞄にしまって、椅子の高さを元に戻した。
「なにか食べたいものとかある?」
「朝はあまり食べないので」
「俺もだよ」
隣人の返答に、また似ている、と思う。
「今日はどうするんですか」
彼はううん、と唸って面倒臭そうに肩を回している。僕と同じように、車の椅子で寝たせいで身体がだるいのだろう。それに彼はまだ眠たそうである。外では雨音は飽きもせずに鳴り響いている。こりゃあしばらく止まないね、と隣人が呟いた。僕の質問へは言葉を返してくれない。寝起きが悪いのだろうか、それともただ不機嫌なのか。
…………
その時、雨音に紛れて何かが聞こえた気がした。よく耳を澄ませてみると、それは子猫のような、掠れたか細い鳴き声だ。彼にも聞こえているだろうかと隣人を見るも、先程と同じストレッチを続けていた。怠そうに身体をひねる彼に問う。
「今猫が鳴きませんでしたか」
「さあね、聞こえなかったけど」
にゃあ
「やっぱり鳴きました! 車の下にいるのかも」
僕は助手席のドアをバン、と開けて、車の下に頭を突っ込むような体制をとる。
「おいおい、濡れるぞ」
隣人は焦ったような声で止めたが僕は構わず車の下を覗き込む。前髪が地面につきそうなほど車の下を見回した。そしてそこにはやはり、子猫がいた。白に灰色の斑模様の小さな猫が、雨に濡れて汚れている。子猫は車体が屋根になっているにもかかわらず流れ込んでくる雨に怯えているようだった。首輪も、首輪のあともないので野良だろうと推測する。僕は顔を上げて、隣人に訪ねた。
「汚れてもいいタオルとかありませんか」
「本気で言ってる?」
「雨が降ってる間だけ。お願いします」
「……仕方ないな」
隣人は顔をしかめながら溜め息をつくと、後部座席に身を乗り出して荷物の中からバスタオルを引っ張りだす。受けったタオルはわりかし前から積んであったもののようで、少し埃っぽい。埃を軽くはらってから膝にタオルを敷いて、車の下に腕をつっこんで子猫を拾い上げた。袖が少し濡れたが気にせず、そのまま子猫を膝に乗せタオルで身体を拭いてやる。子猫は鳴きはしたが、引っ掻くことも噛むこともなく大人しく身体を拭かれていた。
「大人しいですね」
「本当だ、逃げるかと思ったのに」
タオルで拭いて乾かして、きれいにしてやっても、にゃあ、にゃあ、と猫は鳴きやまない。
「……ご飯かな」
そう言って隣人の方を見ると、あからさまに嫌な顔をされた。面倒事に首を突っ込みたくない、という気持ちがありありと顔に出ている。僕は負けじと声を上げた。
「来る途中、コンビニがありましたよね」
子猫が応戦するようにまた、にゃあ、と鳴いた。
「おいおい勘弁してくれよ」
「お願いします」
必死に頭を下げる。子猫は鳴きやまない。彼はまた、深く溜め息をついた。
「いいこだね」
子猫の頭を指でなでれば、にゃあと鳴きながら擦り寄った。隣人は車に積んであった折り畳みの傘をさして、コンビニまで必要なものを買いに行っている。はじめは僕が買いに行くと言ったのだが――隣人の財布でだけれど――車の中で猫と残されるよりもマシだと彼が買い出しに立候補した。
運転席のドアが開いたことで隣人が戻ってきた事に気が付く。彼は外で傘をさしたまま、コンビニの袋を差し出した。すぐさま受け取ってお辞儀をする。
「すみません、ありがとうございます」
「粗相してないだろうね」
彼は睨むが、子猫は大人しく膝の上に座っている。
「はい、良い子で」
隣人はそれを見ると、傘を閉じて車に乗り込んだ。彼ががさつに座れば車が揺れる。苛ついていることは誰が見てもわかるだろう。申し訳ない気持ちを遠のけるように猫を撫でる。
「あとこれ」
よく見ると彼は、たたまれた段ボールを脇に抱えていた。
「雨が止むまで車に置いといていいから、せめてこれにいれて」
隣人が段ボールを組み立てる。ちょうど、子猫が歩き回れるくらいのちいさな箱になった。どこにあったんだろうか、こんなもの。疑問に思っても仕方がないので、大人しく受け取る。苛立っている彼に質問する勇気も、そこまでの興味もなかった。
「わかりました」
渡された段ボールにタオルを敷いて、子猫を中に放す。すっかり猫用としてタオルを使ってしまっているが、それに関しては彼は何も言わなかった。コンビニのビニール袋の中身を見ると、子猫用の餌にミネラルウォーター、それと餌と水を入れる用であろう紙皿が入っていた……やけに用意がいい。
「ミルクじゃなくて大丈夫だよな?」
「はい、多分……その、ありがとうございます」
「べつに」
猫の餌の袋を開けると、少しの量を紙皿にうつした。ミネラルウォーターも同じようにする。段ボールの中にそれらを置くと、子猫はおそるおそるといった様子で匂いを嗅いで、そうっと餌に口をつけた。しばらく食べると水の方にも口をつけて、それで満足をしたのか、のんびりとあくびをしてタオルの真ん中で丸くなる。ゴロゴロと喉をならしている。
「口にあったようでよかったよ」
隣人は雨の降りやまない窓の外を眺めていた。