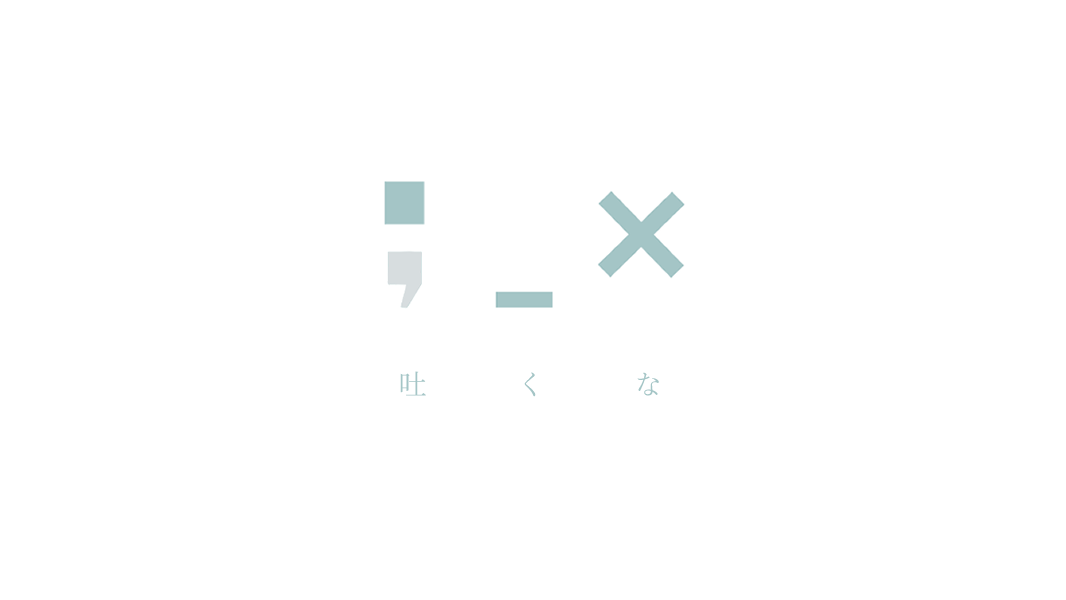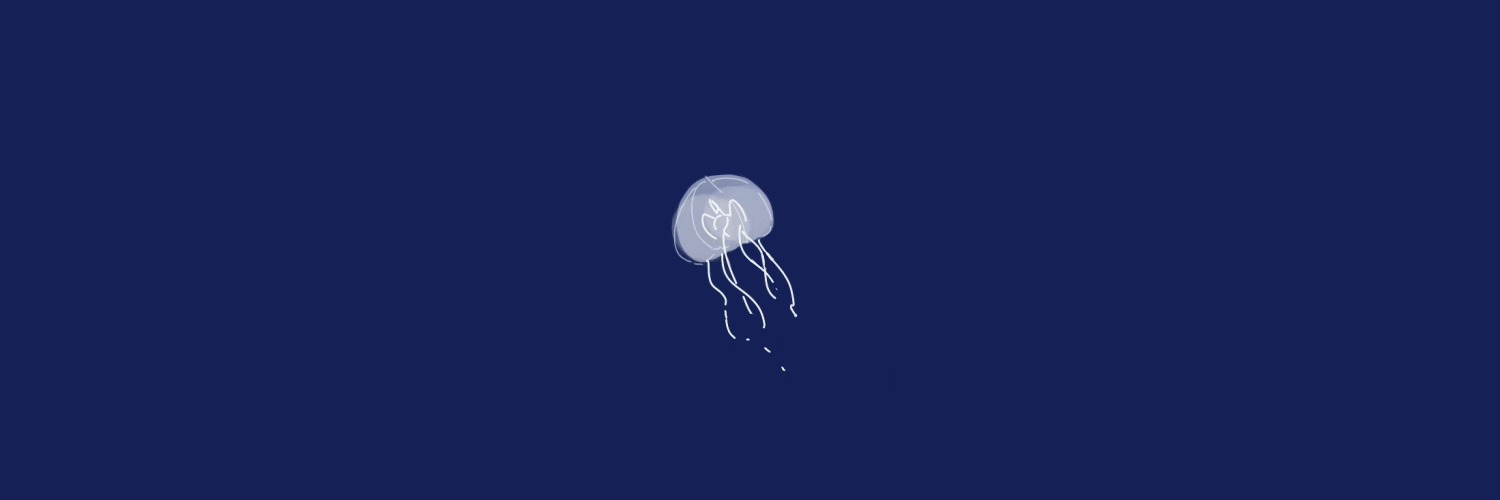仄暗い、死を匂わす表現があります。作中のどの行為も推奨しません。
頭を焦がすような日照りの中、僕はただひたすらに後悔をしながら歩いていた。ニュースによれば気温は三十度を優に超えて、制服の半袖から抜き出た地肌は焼けるように暑い。熱に浮かされた頭の中に鬱陶しいセミの鳴き声が滑り込んでくる。平日の昼間、この暑さのなか屋外に出ている人間は殆ど居ない。そんな中を僕は、通学路を帰る方向にむかって歩いていた。帰宅時間という訳ではなく、単に学校に行けなかったのだ。行かなかった、という方が正しいのかもしれない。いつも通りに通学路を歩いていて、突然足が動かなくなってしまった。このまま歩いて学校に行きたくないと思い立ってしまってからは、数十分は立ち止まっていたと思う。そのうち吹き出る汗とじわじわと迫り来るこの暑さに耐えられなくなって、こうしてアパートまで帰ってきてしまった。
学校を故意に休んだのは、今日が初めての事だった。背中に垂れる汗が罪の意識を加速させる。拭いきれない水滴は制服のシャツをベタつかせて、たまに吹き抜けるそよ風さえも心地のいいものとさせた。雲一つない空は変わらずに青く、夏の色をしている。アパートの階段を登る途中、どこかから風鈴の音がした。まごうことなき夏である。
階段を登りきって、廊下を少し進めば自宅の玄関に到着する。おんぼろアパートの二○三号室が僕と両親が三人暮らしで住む部屋だった。鞄から家の鍵を取り出して、鍵穴にさして回した。両親は仕事で夜まで帰ってこない。学校には行ったフリをしてしまおうか、どうしようかと考える。嘘を付いても学校から両親に連絡が行くのだろうか。立て付けの悪いドアに手をかけると、隣の部屋のドアが開いた。二○四号室、長袖のシャツを捲りながら鍵を閉める隣人は、確か普通の会社員だったはずだ。普段ならもっと早い時間にアパートを出ていく姿を見かけている。いつもは声なんてかけないけれど、彼はよく見掛ける姿よりのんびりとした空気をまとっていたし、学校をサボったことによって気が軽くなっていたのかなんなのか、僕は鍵を閉め終わり顔を上げた彼に声を掛けた。
「こんにちは」
「ああ、おはよう」
噛み合わない挨拶に僕が首を傾げると、彼はしまったという顔をして「今はこんにちはだっけ」と頭を掻いた。無言の間がなんとなく気まずく、僕が言葉を続ける。
「今日は遅いんですね」
「君もね」
「……はい」
会話が続かない。けれどお互いに動こうともしない。部屋の前で立ち止まる隣人の態度にどこか違和感を覚えて、僕は気が付くと口走っていた。
「僕、実は、はじめて学校をサボってしまって」
「そっか……俺もはじめて仕事をサボっちゃった」
こちらは意を決して伝えたのに、彼は何てこと無いようにそう返してきたので、驚いて顔を上げる。そうして隣人の表情を見れば、彼は諦めたような目をしていた。
「いいんですか」
「駄目だね、仕事用の携帯、連絡来っぱなし」
もう辞めるつもりでいたんだけどさ、と彼は溜め息をついた。何を言えばいいか分からず僕が黙ったままでいると、彼はいい事を思い付いた、といったふうに、それでも悪い顔をして笑う。
「せっかくだから、どこか行かない?」
彼は仕事、僕は学校を。はじめてサボったという境遇をどこか重ねてしまったからか、僕は素直に隣人についていくことにした。家の鍵を閉め直すと、階段を降りる彼の後を追いかける。鞄には教科書と筆記用具が入ったままだ。
アパートの裏手、駐車場の花壇には太陽を向いたひまわりが複数、凛と咲いている。花弁の黄色が眩しくて、そっと目を逸らした。隣人はもう車の前に立っている。シルバーのセダンだ。車の鍵が開く音がしたので、僕は当たり前のように助手席に回る。ドアを開けてシートベルトを装着していると、隣人が驚いたような顔で固まっていた。なにかいけなかっただろうか、不思議に思って問いかける。
「……どうかしましたか」
「いや……助手席に誰かを乗せるなんて久しぶりでさ」
彼は驚いた顔を取り繕うように不器用に笑った。セミの合唱は相変わらず、車の中にも漏れ聞こえている。車のエンジンがかかると同時に彼がクーラーを付けた。生温い風と共に、ミント系の芳香剤の香りが鼻を掠める。クーラーはすぐには効かない。車内は外よりも蒸し暑く、隣人は首元のボタンをひとつ外していた。そういえば、彼はネクタイをしていない。会社をサボったからだろうか、それともクールビズというやつだろうか。校則では必ずネクタイを着用しなければならないので、学生の僕にはよくわからないことだった。
「どこか行きたいところは?」
そう尋ねられて行きたいところを思い浮かべる。いきなり行きたいところと言われても、今日一日部屋で過ごすつもりでいたのですぐには思い付かない。僕は逃げを選択した。
「わかりません」
「じゃあ適当に」
隣人がアクセルを踏み込んで、車が発進した。
車の速度に合わせて移り変わる景色は珍しく、サボりという小さな罪を霞ませて少しだけワクワクさせる。毎日毎日、飽きもせず繰り返される日常にうんざりしていたところだった。勉強はそこそこ出来ていれば問題ない、友人は浅く広く。これといった趣味もなく、家に帰ればただいまを言ってもしんとしている薄暗い部屋と、仕事が忙しい両親の代わりにこなしている家事が待っているだけ。
どこへ向かっているのかを考えながらぼんやりと外を眺めていれば、学校を休んだ後悔はいつのまにか薄れていた。隣人がふと口を開く。
「今日さ、なんで声かけたの?」
その問いに口ごもる。はっきり言って理由なんてなかった。僕は普段、相手から声をかけられたりだとか、どうしてもしなければならない状況にならない限りは挨拶をしない質だった。挨拶をしなさいとしつこく教育されたわけでもないし、挨拶が習慣になるほど人と会うわけでもない。どう答えればいいか考えて、答えが見つからない。僕はまた逃げた。
「……わかりません」
「そればっかりだね」
隣人はからりと笑う。隣に住んでいるのだから当たり前に姿は見掛けていたけれど、彼の笑顔を見るのは何故か今日が初めてだと感じた。走行音とクーラーの風音が合さってセミの声が遠くなる。段々とクーラーが効いてくると車内は気持ちのいい涼しさと、くすぐったい芳香剤の香りに包まれた。
「どこに向かってるんですか」
疑問に思って訪ねても、隣人から返ってきたのは「どこだと思う?」という曖昧な質問返しだ。一応考える素振りをしてみるものの、正直検討もつかない。
「ヒント。子供が好きな所、家族連れやカップルもよく行く、癒やしの空間……かな」
「そこに、僕達で?」
「はは」
隣人は思わずといった様子で吹き出した。
「心配すんな、俺の好きな所だよ」
彼の横顔は不器用に笑っていた。