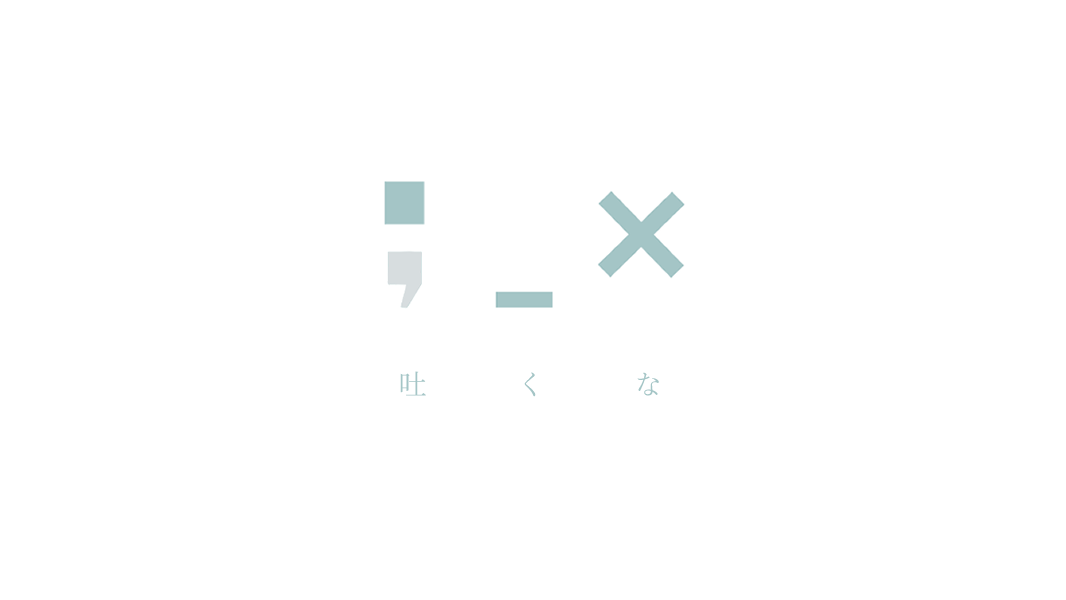猫の平均体温は三十八度から三十九度。最近猫を飼い始めた苑田が得意げに話しているのを聞き流しながらぼくは、窓の外に浮かんでいる入道雲を眺めていた。ぼくが話を聞き流していることに気が付いたのか、それとも単に話し飽きたのか、苑田はそろそろ帰ろうぜ、と笑って学校指定の鞄を手に取る。同じように鞄を背負って、ぼくたちはクーラーの冷気の残った教室から廊下へと出た。この、包み込むような蒸し暑さが嫌いだ。鞄から水筒を取り出して中の水をひとくち含むと、ぼくと苑田は昇降口へと向かった。
「テスト勉強しててもさ、乗っかってくるんだよ、構ってくれってさ。可愛いのなんのって」
「邪魔してるんじゃなくて?」
「ばか、猫っていうのはもっと純粋な生き物なんだ」
おまえに猫の何が分かるんだ。ぼくがそう呟くのを聞き逃さなかった苑田は相変わらずの馬鹿でかい声で反論してくる。
「お前こそ、猫飼ってないのに猫の何を知ってるっていうんだ?」
それから、思い出したようににんまり顔。
「可愛いぞ、猫は。飼わないの? ほんと一回飼えばわかるって。可愛いから」
「あーあー、わかった、わかった」
そのまま自分の家の猫がいかに可愛いかを力説しようとしている苑田をあしらいながら学校の敷地を出る。歩行者用の信号が青になるのを少しだけ待ってからまた歩きだそうとしたところで、隣に苑田が居ないことに気がついて振り返った。彼は近くの日陰を覗き込むようにしゃがみ込んでいる。ため息をつきながら近寄れば、苑田は小声でこう言った。
「こねこ」
「何?」
「子猫だよ、子猫」
なるほど、丁度日陰になっている所に子猫が数匹固まっている。
「可愛いな。捨て猫かな? お前んち飼える?」
「飼わない。てか、親待ってるだけかもしれないだろ」
「そっか、確かに。なら大丈夫だ」
「行こう、ほら。暑いんだから」
苑田は納得したのか、猫撫で声で子猫に別れの言葉を囁いてから立ち上がった。信号はいつのまにか赤に変わっていて、また青になるまで待たなければならない。背中に汗が伝うのを、制服の下に着たシャツが吸い取る。これで風でもあれば涼しいのだけれど、じめじめするばかりで気温も湿度もぼくに優しくない。まだ子猫に手をふっている苑田を置いていくように、信号が青に変わった横断歩道を渡った。
「なんで飼えないの、猫嫌いだっけ?」
「ぼくは別に嫌いじゃないよ」
しっかりと付いてきた苑田は、まだ猫の話題を続けるらしい。水筒を揺らすと氷がステンレスとぶつかって涼し気な音を立てる。
「じゃ、なんで」
「なんでだろ……親が、だめ」
「あー」
苑田は納得すると同時に肩を落とす。
「それじゃあダメだなあ。親はなあ。俺たち子供だもんなあ」
「まあね」
母親が、猫を”だめ”だと言ったのは、たった一回だけだ。
よく晴れた夏の日だった。ニュースでは猛暑、猛暑とひっきりなしで、駅前に設置されたでかい温度計が指すには、三十度を優に越していた、そんな日。そんな記憶がおぼろげにある。
小学校で義務付けられている黄色い帽子を被って、重たい教科書の入った黒のランドセルを背負って、ぼくはその猛暑のなかを家に向かって歩いていた。じわじわと体力を搾り取っていくような暑さが、太陽から、コンクリートから湧き出ていて、まるで蒸されているかのように、きっと湿度も高かった。水筒に入った残り少しの氷水を飲もうと蓋をあけたとき、ぼくはうっかり、水筒のふたを落として、転がした。転がった水筒のふたは脇道にそれて、いつも通らない道へと僕を誘った。そこで見つけたのだ。ちょっぴり砂のついた水筒のふたと、道路に横になっている子猫を。
ぼくは動物が嫌いじゃないほうだ。たとえば給食室から出た野菜の切れ端を、うさぎにやる当番を引き受けるくらいには。だからぼくは汚れてしまった水筒のふたを、砂を払ってからもとに戻してその後に、子猫を拾い上げた。
あったかい。だけど、ぬいぐるみみたい。
やけに柔らかい子猫を抱きながら、ぼくはすぐに、この子を飼いたい、と思った。だって、ちいさくて暖かくて可愛くて、ぼくが守ってあげないとと思ったから。ぼくは帰路を急いだ。子猫は大人しく、暴れもせずに眠っているみたいだった。突然知らない家に連れて行かれたら、びっくりしてしまうだろうか。勝手に連れて帰って、父と母は怒るだろうか。それでも説得しようと思った。だって、こんなに可愛いんだから。
「だって、こんなに可愛いんだぜ? テスト勉強もおろそかになるよなあ」
「勉強できないのを猫のせいにするなよ」
苑田の家につくなり渡された、ねこじゃらしのオモチャを適当に左右に振ると子猫は、苑田の家の子猫は、素早い動きでねこじゃらしを捕まえる。
「だってよ、可愛いんだよお」
「見ればわかる」
「お、わかるか! はっちゃんの可愛さがわかるか!?」
「はいはい」
はっちゃん、というのが苑田の家の子猫の名前だ。ハチワレ柄だからはっちゃん、実に苑田がつけそうな名前である。はっちゃんはぼくの動かすねこじゃらしに必死に食らいついて、疲れる様子もない。
「子猫って、結構活発なんだな」
「ん? まあ、性格によると思うけど……はっちゃんは抱っこが嫌いでさあ、まだ十秒くらいしか捕まっててくれねーの」
「ふうん」
また無意識に――なのか、わざとなのか――惚気はじめる苑田をおいて、ぼくは苑田の母親に頂いた麦茶を飲み込んだ。結露が指をつたう。視界のはしで、動かなくなったねこじゃらしを不思議そうにみつめる子猫……はっちゃんがいる。苑田はまたお喋りを続けている。
「クーラー効いてていいね、苑田の家は」
「お前鍵っ子だもんな。帰ったとき部屋暑いの?」
「暑い。そう思ってクーラーつけっぱで出かけた時はバレて怒られたし」
「そりゃ怒られるわ」
「ま、猫飼うとクーラーつけっぱでも怒られなくなるかもな。猫が熱中症になる室温って三十度なんだぜ?」
「ふうん」
そんな話をしていると、はっちゃんがぼくの膝の上によじのぼってくる。頭をそっと撫でてやる。柔らかい。ブルーの瞳がしっかりとこちらを見つめている。
「可愛いだろ」
「そればっかり」
可愛いのも事実だが、呆れているのも事実だ。
子猫を飼うにはどうしたらいいのか、調べるにもパソコンの電源の付け方もよくわからず、ぼくはとりあえずクーラーのスイッチを押した。暑い部屋に帰ってくるのは慣れていたけれど、この日は特別暑いような気がした。ソファの上に子猫を寝かせる。毛は思ったよりも硬かった。クーラーから涼しい風が出てくると、学校の疲れも重なって、ぼくのまぶたは重たくなった。子猫の隣、ソファに横になる。子猫の毛を撫でつけるようにしながら、一緒に横になる。お母さんが帰ってきたら、猫を飼っていいか聞いてみよう。それで、だめだと言われても、絶対に世話するから、と頼もう。ぼくの分のおやつがなくなるくらいなら構わない。お手伝いだってするし。ごはんもあげられるし。トイレの掃除も、まだ、よくわからないけど。猫って、散歩はいいのかな。お父さんにきこう。飼っていいって、言ってもらうんだ。言ってもらうんだ。クーラーの風を感じながら、ぼくは子猫と一緒に深い眠りについた。
「じゃあ、また学校でな! いつでも遊びにこいよ。はっちゃんも待ってるぞ」
「ああ、うん。ありがと」
苑田に軽く手を振ると、薄暗くなりつつある空を仰ぐ。目が覚めると、母親がいた。父親となにやら難しい顔で話をしていた。ぼくは寝過ごした、そう思ってすぐにソファから起き上がって、叫ぶような声を上げる。というか、思っていたよりも大きな声が出て、自分でも驚いたことを覚えている。猫、飼っていい? だとか、そんな風なことを必死に両親に伝えた。世話もする、勉強も手伝いもがんばる、小さいながら出来ることを必死に伝えた。母親はぼくの言葉を最後まで聞くと、首を横に振った。どうして、と。どうしても、と。飼いたい、と。飼えない、と。また、どうして、と。その時の両親の顔はぼんやりとしか思い出せないけれど、とても、怖い顔をしていたと記憶している。記憶がそうなっている。
「あの子猫はだめなのよ」
母親が眉を下げながらそう言った。茶色い毛の、可愛らしい、子猫だった。気付けば子猫はどこにもいなかった。両親を問い詰めることはできなかった。とても、とても難しい顔をしていた。よく晴れた、とても暑い夏の日だった。ニュースでは猛暑、猛暑とひっきりなしで、駅前に設置されたでかい温度計が指すには、三十度を優に越していた、そんな日。太陽の照る、黒に近い道路はきっと熱を吸収して想像よりずっと暑いものだった。頭をくらくらとさせる暑さの中、子猫が、日照りの道路で眠っていたとして。子猫とはいえ、小学生だったぼくは、捕まえられただろうか。飼い猫である苑田の家の子猫が抱っこが苦手なように、野良なんてとくに、逃げてしまうものじゃないのか。どうしてぼくはその子猫を、ぬいぐるみのように持ち帰れたのだろうか。猫の眠りは浅い。苑田が今日口にしていた言葉のなかのひとつだ。起きていたはずだ。持ち上げたり、なんかしたら。ずっとひっかかっていた。ぼくの動物好きは、両親から引き継がれたもののはずだった。道端の野良猫を見て可愛いねと笑う母親だった。動物園によくつれていってくれる父親だった。猫が熱中症になる室温は約三十度。苑田が今日言っていたことだ。
あの日の子猫はきっと、